遺留分侵害額請求されたら?いきなり請求された時の適切な対応手順!
コラム目次
相続トラブルをできるだけ起こりにくくしてくれるのが「遺言書」です。
ところが遺言書によっては偏った分け方が原因で、受け取り分が少ないと感じる相続人が出てくることもあります。
すると遺産の大半を受け取った相続人に対し、自分たちが正当に受け取れるであろう遺産を請求してくる可能性が考えられます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。
では、このような時一体どうすればよいのでしょうか。
今回は、遺留分侵害額請求されたら・いきなり請求された時の適切な対応手順についてどこよりもわかりやすくご紹介します。
遺留分とは何か?
遺留分とは、民法で定められた法定相続人が相続で受け取れる最低限の保障額のことです。
通常相続では、遺言書が優先されますが、遺言書の内容によっては法定相続人のその後の生活を脅かしかねないケースもあります。
民法では法定相続人の権利、生活、利益を守るため最低限の保障額である遺留分という制度を定めています。
遺留分は法定相続人に保障されている財産の権利であり、ざっくり言えば、遺産の1/2、または1/3に法定相続分の割合をかけた金額を必ず取得することが可能です。
もし仮に遺言書に「遺留分侵害額請求は禁止する」という文言が書かれていても、法定相続人が遺留分を受け取れる権利が優先され失われることはありません。
法定相続人が遺留分を受け取れる権利は、たとえ被相続人であっても侵害することができないということです。
そのため遺留分は相続において法定相続人に認められた極めて強力な権利といえます。
また逆にいうと遺言書通りに相続財産の大半を受け取った相続人にとっては最も警戒すべき権利ともいえます。
遺留分権利者について
法定相続人であっても、遺留分を請求できる人と遺留分を請求できない人に分かれます。
遺留分を請求できる人のことを「遺留分権利者」といいます。
こちらでは遺留分権利者、遺留分割合、遺留分権利者であっても請求できない人たちについてそれぞれご紹介します。
遺留分権利者とはどんな人たちか?
遺留分権利者とは次の人たちです。
①被相続人の配偶者
②被相続人の子(子がいない場合は被相続人の孫など)
③被相続人の父母(被相続人に子や孫などがいない場合など)
他方で、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、遺留分権利者にはなれません。
遺留分割合について
遺留分割合とは、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をした時、どれだけの割合の遺留分を取得することができるのかを決めたものです。
ただし遺留分割合は固定ではありません。
相続人の組み合わせによって異なります。
そのため若干複雑です。
こちらでは遺留分割合についてわかりやすくご紹介します。
①配偶者のみの場合は1/2
②子のみの場合は1/2(子は合計で1/2、2人いる場合はそれぞれ1/4)
③被相続人の父母のみの場合は1/3(父母は合計で1/3、それぞれは1/6づつ)
④配偶者と子の場合はそれぞれ1/4(子は合計で1/4、子が2人いる場合はそれぞれ1/8)
⑤配偶者と被相続人の父母の場合は、配偶者は1/3、被相続人の父母は合わせて1/6(父母はそれぞれ1/12づつ)
⑥被相続人の兄弟姉妹には遺留分はなし
遺留分権利者であっても請求ができない人たち
遺留分権利者の中には遺留分侵害額請求ができない人たちがいます。
一体なぜでしょうか。
こちらでは遺留分権利者であっても請求ができない人たちについて解説します。
①相続放棄をしている人
相続放棄をしている人とは、相続財産に関する権利や義務などを全て捨ててしまった人のことです。
相続放棄をすると遺留分侵害額請求はできません。
相続財産によっては資産だけでなく負債もあります。
資産に対し負債が大きい場合には相続放棄をすることも可能です。
また相続放棄をしている人が遺留分権利者だった場合、子や親も遺留分を受け取ることができません。
②遺留分を放棄している人
遺留分を放棄している人とは、遺留分に関する権利を手放した人のことです。
遺留分を放棄すると遺留分侵害額請求はできません。
ただし遺産の相続権は手放していないので遺産相続はできます。
また子や親も遺留分を受け取ることができません。
③相続欠格者になっている人
相続欠格者になっている人とは法定相続人としての資格がはく奪されている人のことです。
相続欠格者になっていると遺留分侵害額請求はできません。
相続欠格者になる理由は一般的には被相続人や相続人の相続に対し、何かしらの犯罪や不正行為などに関与している時です。
ちなみに相続欠格者の子どもは代襲相続人になれ、遺留分権利者にもなれます。
④相続廃除されている人
相続廃除されている人とは家庭裁判所の審判によって相続権をはく奪された人のことです。
相続廃除されていると遺留分侵害額請求はできません。
相続廃除されている理由は被相続人に対して肉体的、精神的な虐待や被害などを与えている場合です。
条件を満たし家庭裁判所で訴えが認められれば相続権をはく奪することが可能です。
相続廃除されている人は遺留分権利者になれません。
ただし子どもがいる場合には代襲相続が発生し、遺留分権利者になれる場合があります。
⑤すでに時効を迎えている人
すでに時効を迎えている人とは時効の期限までに遺留分侵害額請求をしなかった人のことです。
すでに時効を迎えていると遺留分侵害額請求はできません。
時効の期限については遺留分侵害額の請求権の消滅時効・除斥期間に詳しく記載しております。
遺留分侵害額の請求権
遺留分侵害額の請求権とは、遺留分を侵害された相続人が、遺言書通りに相続財産の大半を受け取った相続人に対して遺留分相当額を請求できる権利のことです。
遺留分侵害額の請求権は「民法第1046条第1項」によります。
遺留分侵害額の請求権の期間制限
遺留分侵害額の請求権には期間制限があります。
①消滅時効
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が被相続人が亡くなった事実と遺留分を侵害する遺言書の内容、または贈与を知ってから1年間以内に行使しないと、時効により消滅してしまいます。
②除斥期間
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が被相続人が亡くなった事実と遺留分を侵害する遺言書の内容、または贈与を知らなくても、相続が開始されてから10年以内に行使しないと、除斥期間経過により消滅してしまいます。
いきなり遺留分を請求された時の適切な対応手順
初めての相続の時、いきなり遺留分を請求されると、これまで遺産相続の経験がない人はびっくりするかもしれません。
まずは落ち着いて、各状況に応じてそれぞれの対応を順序通りに行うことをおすすめします。
こちらではいきなり遺留分を請求された時の適切な対応手順についてご紹介します。
①そのまま放置しない
もし他の法定相続人から遺留分侵害額請求をされたら、絶対にそのまま放置しないようにしましょう。
もしそのまま放置してしまうと、家庭裁判所で調停の申立てをされる可能性があります。
調停に入ると双方から事情を聴き、もし遺留分権利者の方が正しければ遺留分侵害額請求に応じるように説得されます。
また説得にも応じないと、いよいよ裁判を起こされるかもしれません。
もしそのまま放置していると、裁判を起こされ、財産の差し押さえをされる可能性があります。
遺留分侵害額請求をされた時には必ず対応するようにしましょう。
②遺留分権利者の主張をそのまま信じない
遺留分権利者の主張をそのまま信じないようにしましょう。
理由は遺留分権利者の中には、遺留分侵害額請求に関してよくわかっておらず自分に都合のいい主張をしてくる人もいるからです。
その場合、遺留分侵害請求に関する次の点を確認してください。
・遺留分侵害額請求をしてきた法定相続人にそもそも資格があるのか、ないのか
・請求された遺留分侵害額が正しいのか、どうか
・遺留分侵害額請求をしてきた法定相続人に生前贈与があったか、なかったか
自分で調べるか、できない場合にはできるだけ早い段階で遺留分侵害請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
③寄与分を要求してくる人には払う必要がない
遺留分侵害額請求に関して、寄与分を要求してくる人には払う必要がありません。
できるだけ相続財産が欲しい人の中には、相続だけでなく、遺留分においても寄与分を要求してくる可能性があります。
寄与分とは被相続人の財産の保持や増加に尽力してきた人に、他の相続人より相続財産を割り増しで分けてもらえる制度のことです。
被相続人の事業を無報酬で働くことや、被相続人を介護したことなどで、5つの条件を満たすと相続財産を多くもらうことができます。
ただし寄与分は遺留分の算定には考慮されないので遺留分として一切払う必要はありません。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求をされるとどんな流れで進むのでしょうか。
こちらでは遺留分侵害額請求の流れについてご紹介します。
①相続人同士での話合い
遺留分侵害額請求をされた場合には、まずは相続人同士で話し合いが行われます。
話し合いで合意に至れば穏便に解決することも可能です。
話し合いでは遺言書の優先性の原則、遺留分侵害があった場合には侵害額の正確な算出、返金額や返金期日などを決め、合意書が作成されます。
遺留分義務者、遺留分権利者の双方が遺留分について正しく理解し、侵害額を正確に把握することで大きなトラブルを避けることができます。
②遺留分侵害額請求に関する通知の送付
もし当事者同士での話し合いで合意に至らなかった場合には、遺留分義務者宛てに遺留分侵害額請求に関する通知が送られてきます。
通常、通知は内容証明郵便です。
通知だからといって絶対に無視せずにすぐに対処するようにしてください。
内容証明郵便で送られてくると、調停や訴訟に発展した場合、法的な証明になります。
すると遺留分義務者が知らない間に状況がどんどん進んでしまい取り返しのつかない状況になるおそれがあります。
③家庭裁判所での調停
遺留分侵害額請求に関する通知が送られてきた場合には、調停の申し立てに移行するケースが一般的です。
調停とは家庭裁判所の調停委員が双方の間に入り、公式な場での話し合いによって問題の解決を図る制度のことです。
話し合いによって双方から合意を得られれば調停成立で、調停調書が作成され、お互いに合意した内容で手続きが進められます。
また調停不成立の場合には次の段階に移ります。
④訴訟が行われる
調停が失敗した場合には訴訟になる可能性があります。
遺留分権利者から遺留分侵害額請求訴訟が提起され訴訟が始まります。
裁判官によって判決が下され、遺留分侵害額請求に関する結論が出されます。
遺留分に関する法改正
2019年7月1日の民法改正により、遺留分に関する法改正が行われました。
改正点のポイントは次の4点です。
①名称の変更「遺留分減殺請求(旧法)」 ⇒ 「遺留分侵害額請求(新法)」
②現物返還から金銭での清算に限定
③特別受益(生前贈与)の範囲を、全て計算対象だったものが亡くなる前10年間に限定
④即時返還から、支払いに猶予を持たせるに変更
遺留分1000万円の返金請求の事例(トピックス)
こちらは実際にあった遺留分侵害額請求の事例を元に、遺留分1000万円の返金請求の件についてご紹介します。
関係者は次の通りです。
被相続人:父
遺留分義務者:兄
遺留分権利者:妹
相続財産:不動産、預貯金
父がすべての遺産を兄へ相続させるとの遺言書を作成していたため、兄が父の全ての遺産を相続しました。
妹は兄に遺産の配分が偏っているとして話し合いを要求しましたが取り合ってもらえません。
そこで妹は弁護士に調査を依頼し、遺産目録を作成し、遺留分額を計算すると1000万円が算出され、これを遺留分侵害額請求として内容証明で兄に送ります。
すると遺産総額と遺留分額の計算が正確だったことから、兄は争ってもムダと判断し支払いに応じてくれました。今回のように遺留分侵害額請求が調停・訴訟まで進まず、話し合いで済む場合は弁護士への依頼費用は安く済むケースもあります。そのためできるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
今回は遺留分侵害額請求されたら・いきなり請求された時の適切な対応手順についてご紹介しました。
相続対策に「遺言書」はかなり有効です。
ただし遺言書の内容が偏っていたり、不完全だとかえって相続を混乱させる可能性があります。
その顕著な例が「遺留分の侵害」です。
中には相続人同士が抜き差しならない関係にまで発展してしまうことがあります。
そうなっては手遅れです。
弁護士に相談することで次の3つのメリットを得ることができます。
・遺留分の侵害の是非を判断してくれる
・代理人として交渉をしてくれる
・遺言書作成、遺言書執行者のサポートが依頼できる
もし遺留分侵害額請求をされた場合には、ぜひ一度エミナス法律事務所に相談してみることをおすすめします。
執筆者プロフィール
- 累計1300件以上の相続相談に対応し、NHKの番組でも『遺産相続問題に詳しい弁護士』としてご紹介いただきました。相続に関する書籍も多数出版しています。難易度の高い相続案件も対応可能です。初回相談では、相談者の方のお話をじっくりお伺いし、相談者の方の立場に立って考え抜き、できるだけ簡単な言葉で分かりやすく説明することを心がけています。
最新の投稿
- 2025年7月25日コラム相続人以外の貢献も報われる!「特別寄与料」と生前対策の重要性
- 2025年7月18日コラム遺産相続の相談先どこがいい?【弁護士が徹底解説】最適な専門家選びとトラブル解決の道筋
- 2025年6月13日遺書と遺言書の違いを弁護士が徹底解説!
- 2025年5月2日【相続で介護の寄与分が認められるために必要な6つの要件とは?】判例と計算方法を弁護士が解説
その他のコラム
相続人以外の貢献も報われる!「特別寄与料」と生前対策の重要性
コラムはじめに 相続の場面では、法定相続人ではない親族が被相続人(亡くなった方)に多大な貢献をしたにもかかわらず、遺産を直接受け取ることができないという問題がありました。例えば、長年、義理の親の介護に尽くしたお嫁さんなどがこれに該当し、その献身的な貢献が報われないという不公平が生じていました。このような不公平を解消するため、2019年の民法改正で「特別寄与料」という新たな制度が創設
遺産相続の相談先どこがいい?【弁護士が徹底解説】最適な専門家選びとトラブル解決の道筋
コラム「大切な家族が亡くなり、遺産相続の手続きに直面したけれど、どこに相談すればいいのか分からない…」「遺産分割で家族間の意見が食い違いそう…」「相続税がどれくらいかかるのか不安…」 遺産相続は、誰もが一度は経験する可能性がある一方で、その手続きや法律の知識は非常に複雑で、多くの方が「何から手をつければいいのか分からない」と悩みを抱えています。もし、相続人間で意見の対立があれば、精神的な負担はさら
遺産分割における預貯金の配分方法の完全解⁉
コラム相続が発生した場合には、被相続人が残した相続財産の中に銀行等の金融機関における預貯金があることが通常でしょう。 相続人が1名のみである場合はともかく、複数名の相続人がいる場合、相続財産を構成する預貯金の配分(取り分)をどのようにすればよいのでしょうか。 「誰がどれだけの配分を受けることができるのか」ということはもちろん、その配分方法も気になるところです。 ・口座を解約して預貯金を
【相続放棄】前後にしてはいけないこと|財産処分の注意点を解説
コラム相続放棄のことで悩んでいる方は必見。この記事では相続放棄の前後にしてはいけないことや注意点について詳しく解説しています。実は知らずに行動すると、放棄の効力が認められない可能性があるのです。この記事を読めば、相続放棄前後の正しい対応方法が分かります。 「相続放棄の手続きをしたけど、故人の遺品の片付けや携帯電話を解約しても大丈夫だろうか?」と悩んでいませんか?実は相続放棄の前後にしてはいけないこ
遺留分侵害額請求されたら?いきなり請求された時の適切な対応手順!
コラム相続トラブルをできるだけ起こりにくくしてくれるのが「遺言書」です。 ところが遺言書によっては偏った分け方が原因で、受け取り分が少ないと感じる相続人が出てくることもあります。 すると遺産の大半を受け取った相続人に対し、自分たちが正当に受け取れるであろう遺産を請求してくる可能性が考えられます。 これを「遺留分侵害額請求」といいます。 では、このような時一体どうすればよいのでしょ
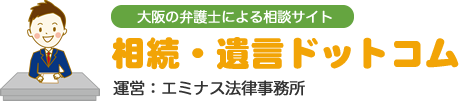
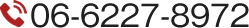



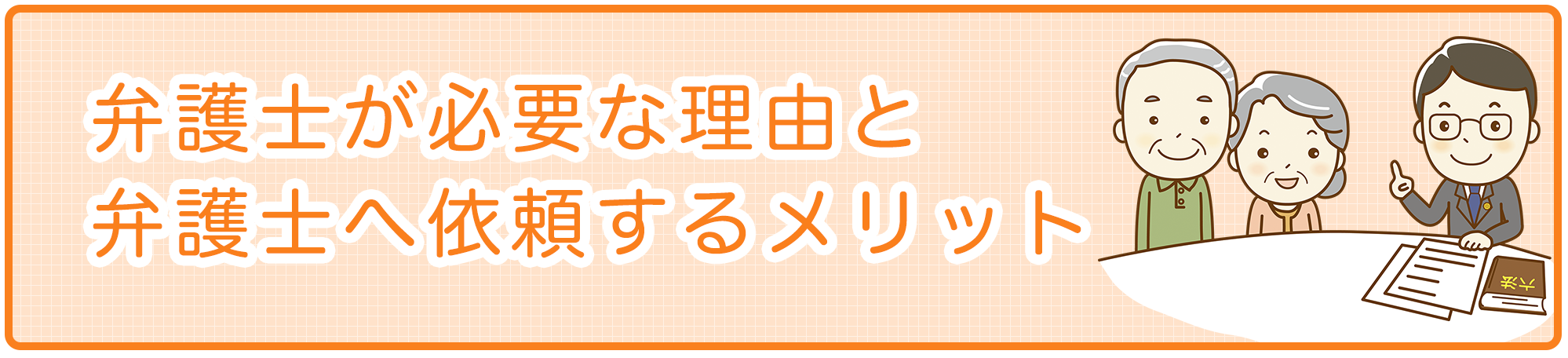
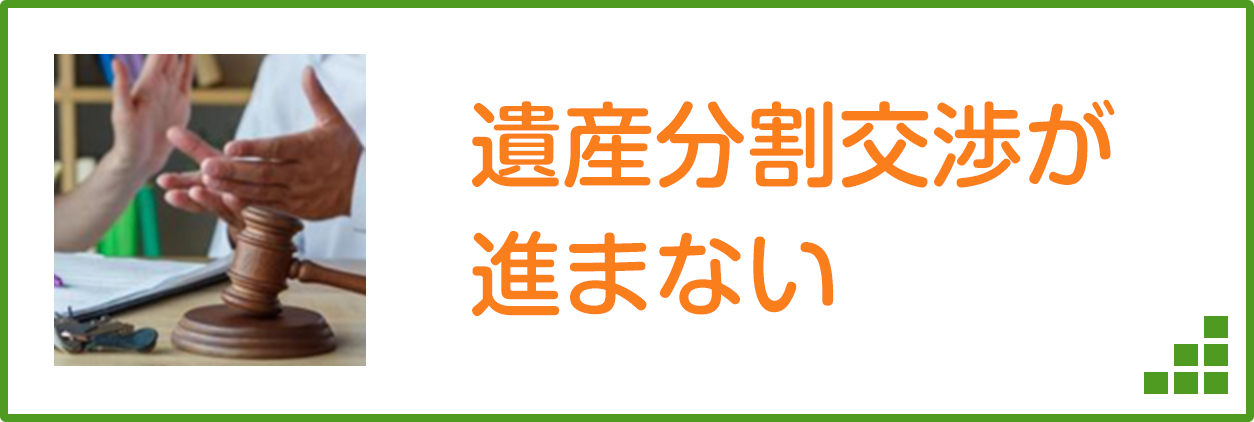

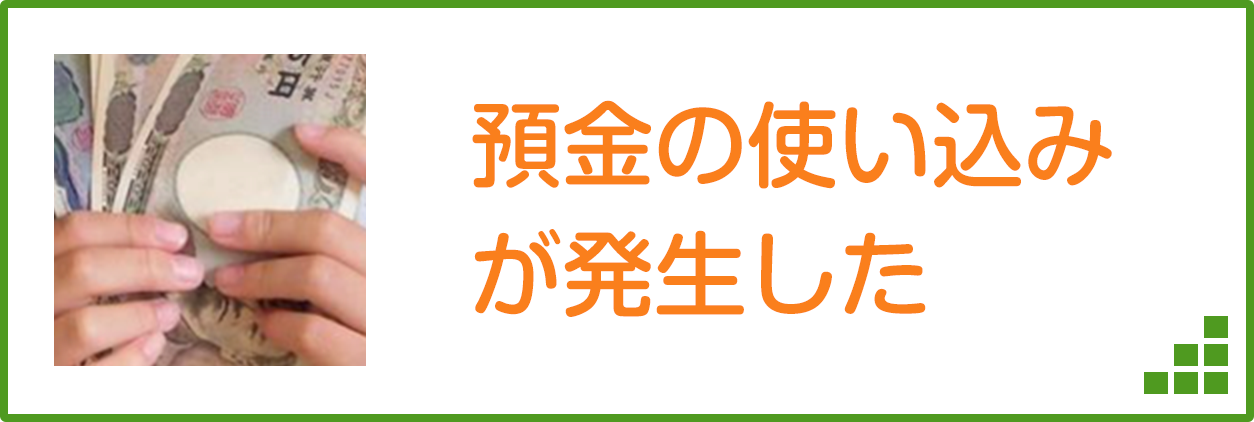

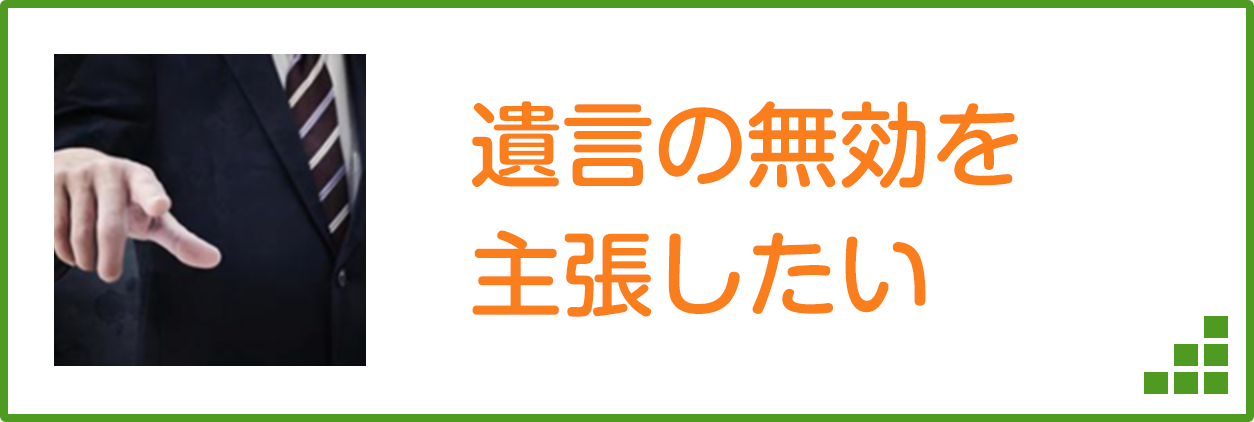
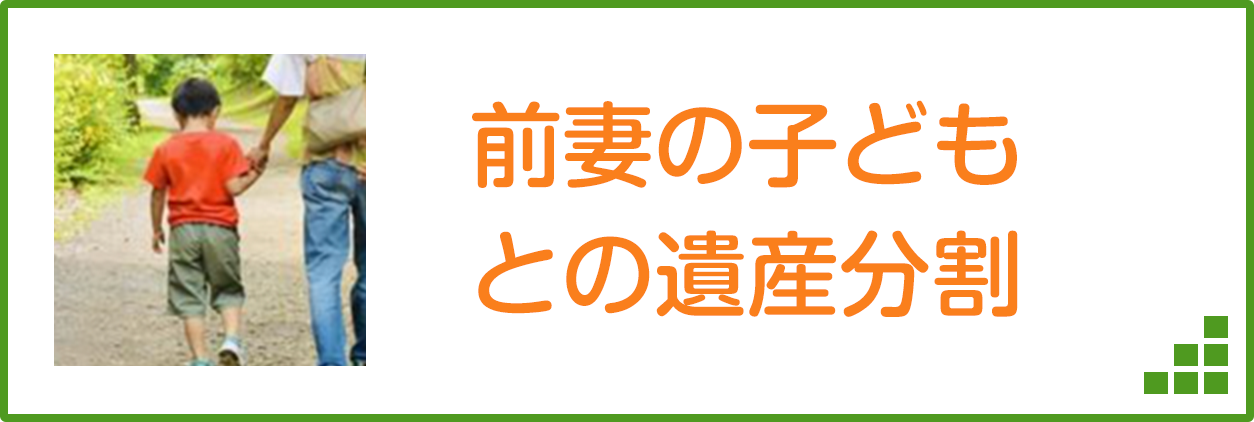
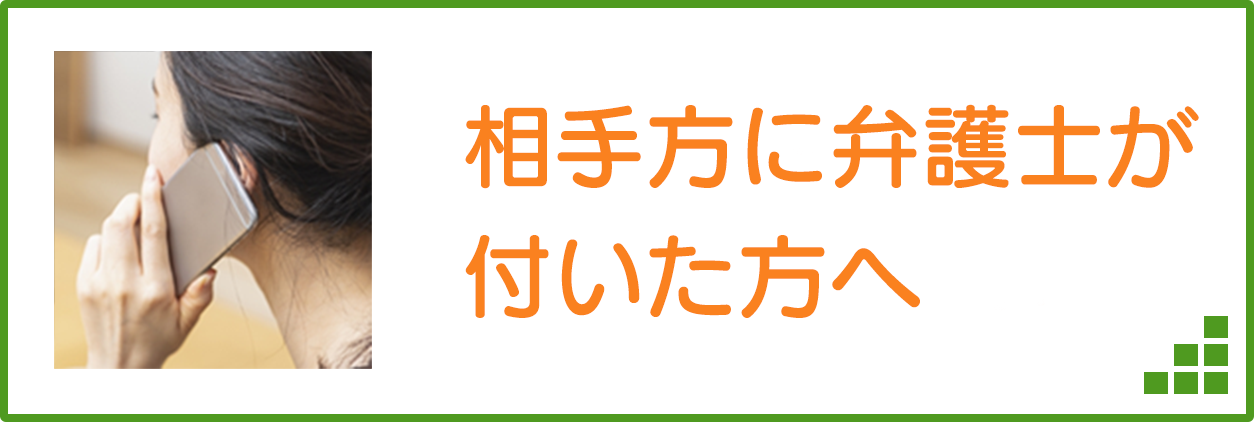
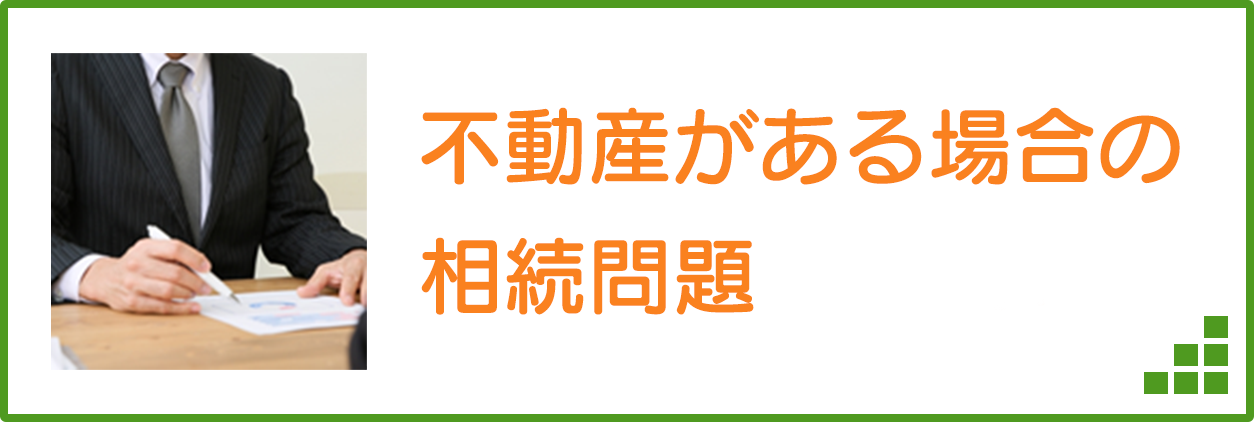


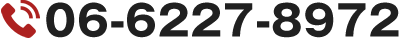






代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
リーガルサービスの提供を通じてお客様を笑顔にしたいとの思いから事務所名を「エミナス法律事務所」(笑みを為す)としました。
お客様を笑顔にするためには、出来るかぎりご希望に沿ったベストな解決を図る必要があります。
ご希望に沿ったベストな解決を図るためには、お客様のお話をじっくりと丁寧にお聞きすることが何より大切です。
そのため、当事務所では、十分なお時間を取り、まずは、お客様が抱いておられるご不安や紛争の解決方法に関するご希望を正確に理解するよう努めています。
その上で、ご不安を解消あるいは低減できるよう、ご納得いただけるまで何度でもお答えさせていただくとともに、どこまでもお客様に寄り添い、笑顔になれる解決を全力でサポートいたします。