相続と債務
金銭債務
- 金銭債務は、相続により当然に共同相続人が法定相続分に応じて分割して承継することになります(最判S34.6.19)。
- 仮に、共同相続人間で法定相続分と異なった内容で債務を承継する旨の合意を成立させたとしても、債権者(金融機関など)が承諾しない限り、債権者との関係で責任を免れることはできません。
- 例えば、相続人が子ABの2人で、被相続人に1000万円の債務があった場合、AB間で、Aが800万円、Bが200万円の債務を承継する旨の合意をしたとしても、金融機関から500万円の支払いを請求されたBは、上記合意があったとしても、500万円を支払わなければ金融機関との関係で責任を免れることはできません。
- ただし、上記合意はAB間では有効ですので、500万円を支払ったBはAに対し、余分に支払った300万円の償還請求はできます。
連帯債務
- 連帯債務についても、相続により当然に各相続人が法定相続分に応じて債務を承継し、その承継した範囲内で主債務者(本来の債務者)と連帯責任を負担することになります。
保証債務
- 保証人が死亡した場合に、保証人である被相続人が負担していた保証債務を相続人が承継するかどうか(=相続性が認められるかどうか)は、保証債務の内容によって異なります。
- 連帯保証を含む通常の保証については、相続性が認められます。
- 相続開始時に現実に発生している主債務の限度において保証責任を承継し、相続開始後に発生した主債務については保証責任を承継しないことになります。
- 責任の限度額・期間について定めのない場合、特段の事由のない限り、相続開始時に現実に発生している主債務の限度において保証責任を承継し、相続開始後に発生した主債務については保証責任を承継しないことになります。
- 相続性が認められると考えるのが判例(大判S9.1.30)・通説です。
通常の保証
身元保証
信用保証(根保証、継続的な取引から生じる債務を包括的に保証するもの)
最判S37.11.9
継続的売買取引について将来負担することあるべき債務についてした責任の限度額ならびに期間について定めのない連帯保証契約においては、特定の債務についてした通常の連帯保証の場合と異なり、その責任の及ぶ範囲が極めて高判となり、一に契約締結の当事者の人的信用関係を基礎とするものであるから、かかる保証人の地位は、特段の事由のない限り、当事者その人と終始するものであって、連帯保証人の死亡後生じた主債務については、その相続人において、これが保証債務を承継負担するものではないと解するを相当とする。
賃貸借契約の保証債務
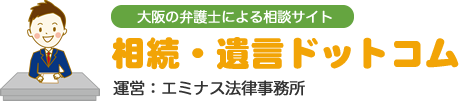
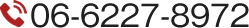



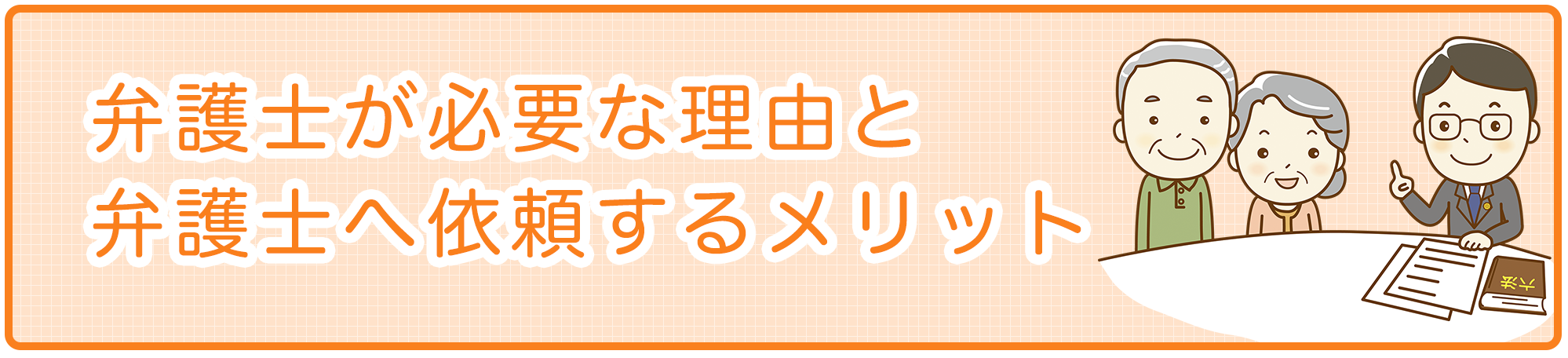
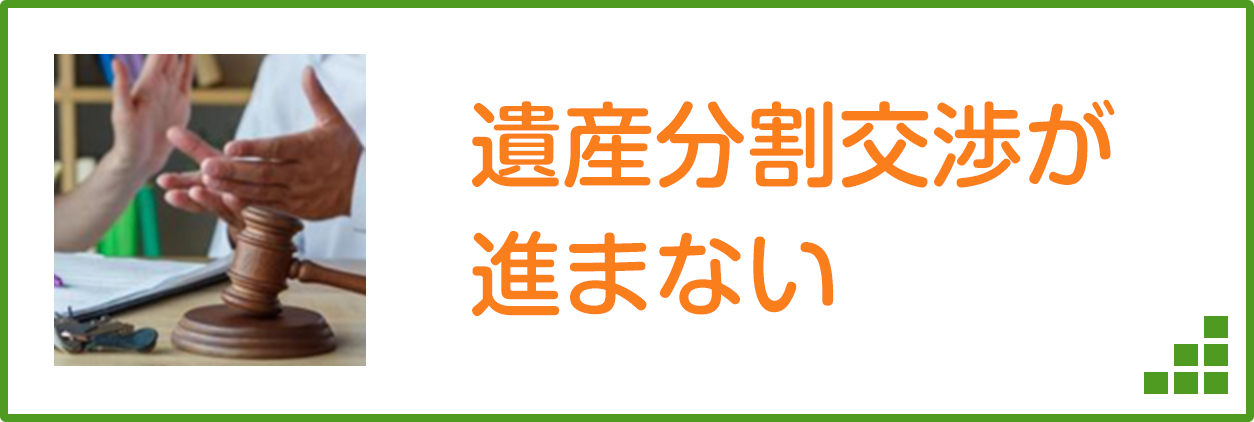

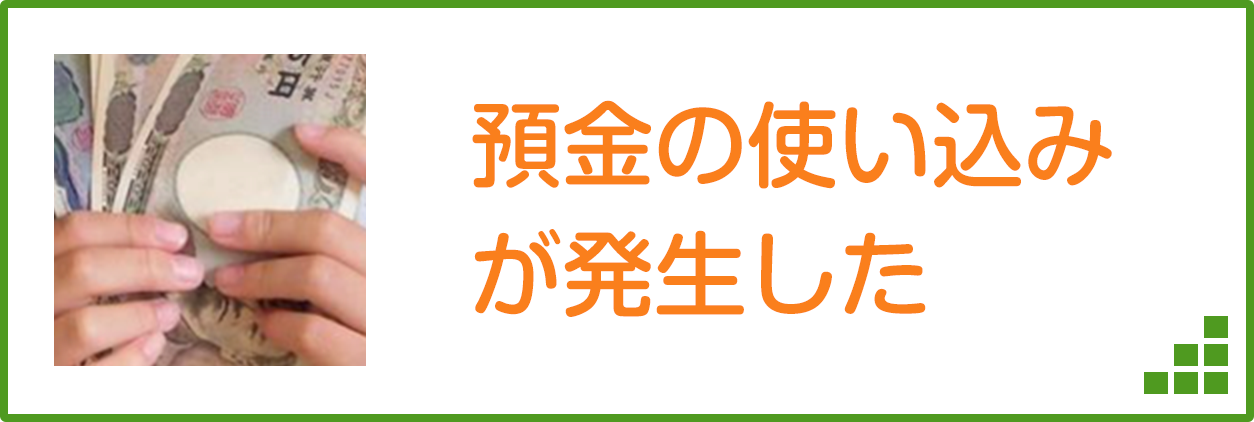

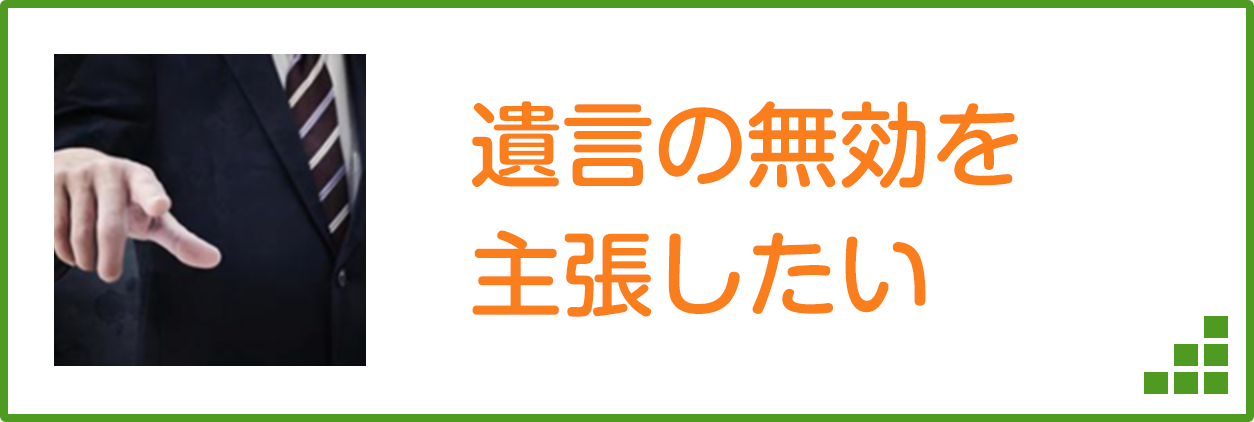
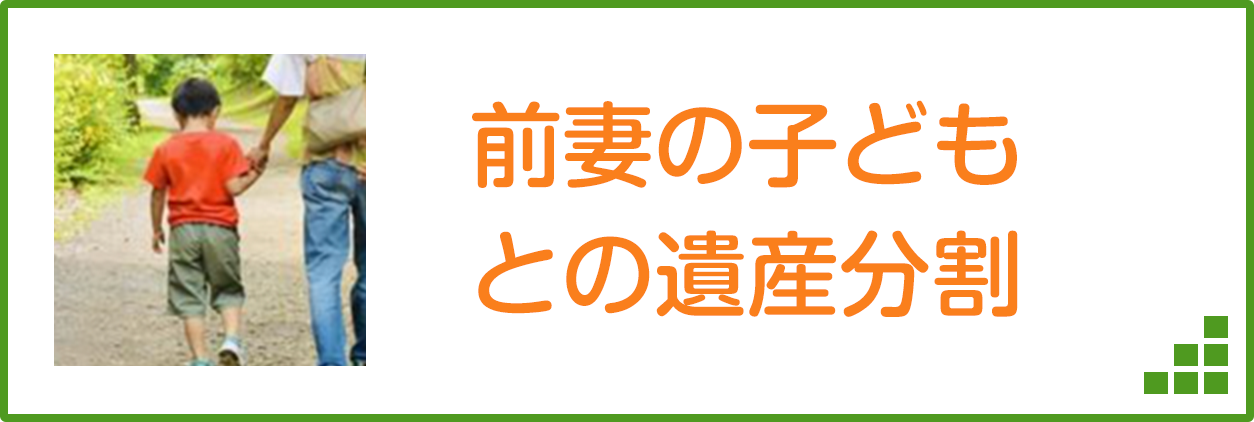
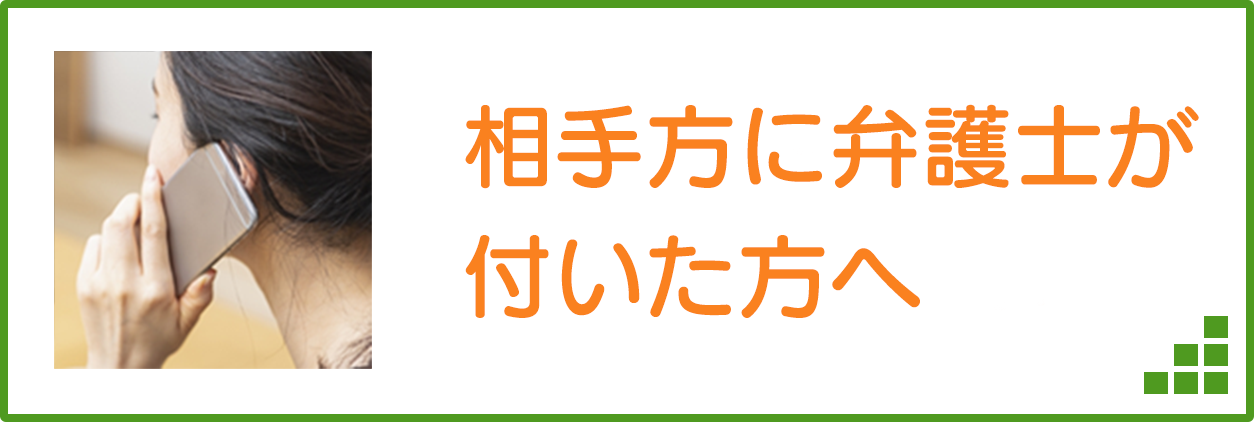
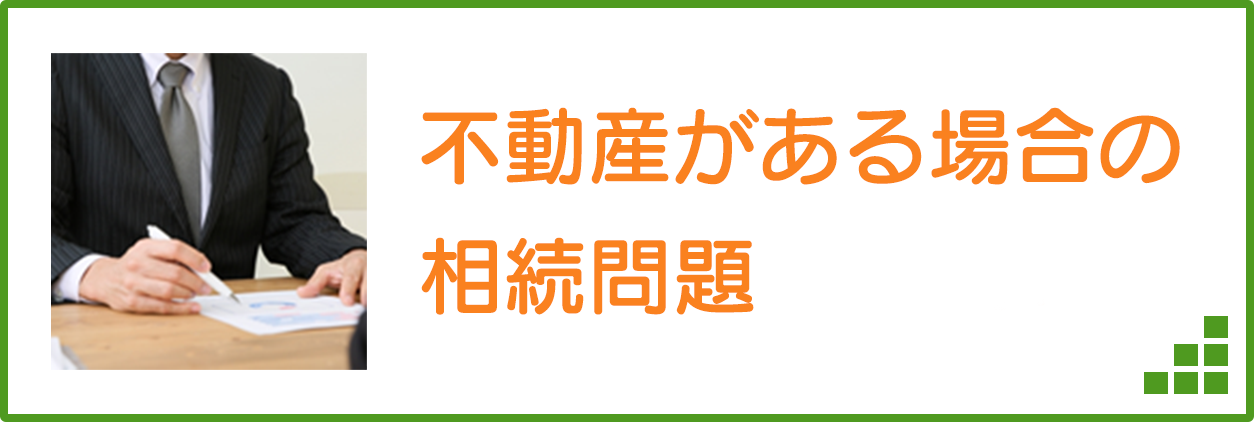


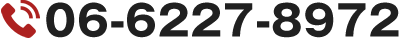






代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
リーガルサービスの提供を通じてお客様を笑顔にしたいとの思いから事務所名を「エミナス法律事務所」(笑みを為す)としました。
お客様を笑顔にするためには、出来るかぎりご希望に沿ったベストな解決を図る必要があります。
ご希望に沿ったベストな解決を図るためには、お客様のお話をじっくりと丁寧にお聞きすることが何より大切です。
そのため、当事務所では、十分なお時間を取り、まずは、お客様が抱いておられるご不安や紛争の解決方法に関するご希望を正確に理解するよう努めています。
その上で、ご不安を解消あるいは低減できるよう、ご納得いただけるまで何度でもお答えさせていただくとともに、どこまでもお客様に寄り添い、笑顔になれる解決を全力でサポートいたします。