遺産分割における預貯金の配分方法の完全解⁉
コラム目次
相続が発生した場合には、被相続人が残した相続財産の中に銀行等の金融機関における預貯金があることが通常でしょう。
相続人が1名のみである場合はともかく、複数名の相続人がいる場合、相続財産を構成する預貯金の配分(取り分)をどのようにすればよいのでしょうか。
「誰がどれだけの配分を受けることができるのか」ということはもちろん、その配分方法も気になるところです。
・口座を解約して預貯金を分割して相続人各人が振り込みを受けるのか。
・口座をまるごと相続して、銀行等の金融機関所定の方法に従って名義変更手続きを行うのか。
・他の相続財産を含めて全体との調整を行うのか。
実際の相続の現場は、非常に慌ただしく、大切な親族を失ったことに対する悲しみに浸ることは困難であり、多くの手続きを踏んでいく必要があることを痛感する場でもあります。
特に初めての相続を経験するのであれば、なおさらです。
この記事では、相続財産に預貯金がある場合の諸手続きを初めて行う人であっても、その対応に困ることがないよう、必要な事項を解説することを目的としています。
このため、相続について十分な知識をお持ちでない読者であったとしても、この記事を読むことにより上記の事項について銀行等の金融機関との間で適切な連絡を取り、必要な手続きを遺漏なく行うことができるようになります。
ぜひ最後までお読みください。
相続財産における預貯金の特殊性
まずは、相続に関する諸手続きを行うにあたり、相続財産としての預貯金の特殊性を知っていただく必要があります。
実は、金融機関においては、預貯金については、原則として遺産分割をした後でないと払い戻しができないという取扱いがなされているのです。
払戻しには、相続人全員の合意が必要
相続人としては、相続財産を構成する預貯金について、相続し得る権利を有するとしても、各自が単独で権利行使することはできず、相続人全員の合意を必要とするのです。
実は、従前においては、預貯金は遺産分割の対象外であるという取扱いがなされており、法定相続分の範囲内であれば金融機関より単独での払い戻しを受けることができていました。
ところが、その後、最高裁において預貯金も遺産分割の対象になる旨の決定(平成28年12月19日付)が出されたことを契機として、相続財産における預貯金の取扱いに変更が生じたのです。
<最高裁平成28年12月19日決定の要旨>
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。
この最高裁決定は、それまでの裁判所を考えを変更したものであると評価されています。
最高裁決定の相続実務に対する影響
次に、上記の最高裁平成28年12月19日決定が与える相続実務に対する影響について纏めておくことにします。
家庭裁判所実務に対する影響
家庭裁判所の実務においては、従来より金融機関に対する預貯金については、相続当事者全員の合意がある場合にのみ、遺産分割の対象とする取扱いがなされていました。
それが、上記平成28年12月19日の決定により、相続当事者間における合意の有無やその内容に関わることなく、預貯金が遺産分割の対象となることが位置付けられたのです。
このため、相続人の中に特別受益を受け、あるいは寄与分がある場合においても、預貯金の遺産分割により実質的公平の確保がなされやすくなったと評価されています。
銀行等の金融機関実務に対する影響
平成28年12月19日の最高裁決定以前においては、金融機関に対する預貯金は金銭債権である以上、可分債権であるから、相続人各人に対して分割されるとの立場に立脚していました。
そのため、従前において各相続人は、法定相続分に応じて自己の取り分の払戻しを金融機関に対して請求できていたわけです。
金融機関においても、遺産分割に伴う無用な混乱を回避するためには相続人全員の合意による払い戻しを基本としつつ、全員による合意が困難な事情がある場合には、相続人各人による法定相続分に応じた払い戻しを行うことにしていました。
そうした中、上記の最高裁決定を受け、以後は基本的に遺産分割がなされない状況においては払い戻しを行うことはできないこととなったわけです。
相続人間における預貯金の配分方法
ここでは、相続人間で金融機関に対する預貯金を配分する際の方法・必要書類について説明します。
被相続人の遺言がある場合
預貯金の相続にあたり、被相続人の遺言がある場合には、その遺言の内容に従って相続人に配分を行うことになります。
もっとも、遺言は民法において厳格な要式性が求められ、法定されている事項以外は、たとえ遺言の中に書き入れたとしても、法律上の遺言としての効力を有しないこととなるのです。
その趣旨は、遺言の効力が発生した時点(遺言者が死亡した時点、民法第985条第1項)においては、もはや遺言者は権利能力の主体としての地位を失っており、その真意を確認することができないため、可能な限り疑義が生じることを避けることにあります。
民法は、普通方式の遺言として、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類を用意しています。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、次の事項をすべて自書するとともに、押印することが必要です。
• 遺言の内容となる全文
• 日付
• 氏名
自筆証書遺言は、その方式が簡単であり、特段の費用もかからないことが最大のメリットであるといえます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、次の事項を要件とします(民法第969条)。
・証人2人以上の立会いがあること
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
・公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること
・遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印すること
・公証人が、その証書は所定の方式に従って作成したものである旨を付記して、これに署名し、押印すること
公正証書遺言の場合その原本と正本が作成され、原本は公証役場に保管され、正本が遺言者に対して交付されます。
公正証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、法律専門家である公証人が作成に関与するため、民法が採用する遺言の様式性を担保することができるだけでなく、内容の不明確性を避けることもできることが最大のメリットです。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、次の事項を要件とします(民法第970条)。
・遺言者による証書への署名押印
・遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもって封印すること
・遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名および住所を申述すること
・公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し、押印すること
被相続人が遺した遺言が要式性を具備したものとなっているか、不安がある場合には、相続問題に詳しい法律専門家としての弁護士に相談することが確実です。
また、各金融機関で手続きを行う際に必要な書類については、各金融機関の相談窓口を通じて確認しておくことが手続きをスムースに進めるコツです。
被相続人の遺言がない場合
次に、被相続人の遺言(書)がないという場合も少なくありません。
この場合には、相続人間で遺産分割協議を行い、預貯金の配分(取り分)を決めていくことになります(遺産分割協議書を作成します)。
相続人間の配分を決める方法(概要)は、次のとおりです。
法定相続分等により相続人間の配分(取り分)を定める
基本的には、法定相続分によることが通常です。
しかし、法定相続分による配分は絶対的なものではなく、相続人全員の合意を得られるならば、法定相続分とは異なる配分とすることもできます。
預貯金の分割方法を選択する
相続人間で取り分が決まった場合には、次に預貯金の具体的な分割方法を定めることになります。
その分割方法は、次のとおりです。
・口座を解約し、分割した預貯金の振込みを受ける
・預金口座自体を相続し、口座名義を変更する
・他の相続財産と調整する
相続財産調査
被相続人の財産(遺産)がどの程度あるのか、その全体を把握することができなければ、相続人間で円滑な遺産分割協議は実現することは困難です。
このため相続財産調査を行うことが肝要です。
特に預貯金については、銀行等の金融機関の通帳、キャッシュカード、金融機関の口座へのログイン情報等を探します。
金融機関各社からの郵便物等により手がかりをつかむこともできます。
手がかりをつかむことができた場合には、当該金融機関に対して連絡し、口座名義人が他界し、相続が開始した旨を伝えることになります。
その際、金融機関各社所定の手続き方法について説明を求めるとともに、必要な書類・提出期限等の情報を郵送等により提供してもらえるよう、依頼しておくと以後の手続きがスムースに進むことにつながります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、全ての相続人間において実施し、合意に至った遺産分割協議の内容を記録した書類を指します。
遺産分割協議書は、金融機関に対する相続手続きを行うにあたり、重要な書類です。
もっとも、金融機関各社が重要視するのは、相続人間で合意に至った事実とその内容ですので、金融機関の中には各社が手続きを行うにあたり、相続人間の合意内容を明記させる所定の手続様式を準備し、特に遺産分割協議書という名称の書類をあらためて準備することを要しない場合もあります。
また、遺産分割協議書ないしこれに代わる上記のような金融機関所定の様式を準備するにあたっては、法律専門家としての弁護士の関与を必須とするものではありません。
しかし、必要事項の記載漏れ等の事態を避けるとともに、相続人間での無用なトラブルの発生を未然に防止する意味では、中立的な立場にある弁護士のチェックを受けることも検討してみると良いでしょう。
なお、大手都市銀行である三菱UFJ銀行の遺産分割協議書の取扱い方針について、以下に紹介するので、読んでみることをおススメします。
参照ページ
遺産分割協議書とは?作成の流れや手続きを解説 | 三菱UFJ銀行
相続人が特に注意しておくべき事項
この項では、相続人が預貯金を相続する場合における注意点を説明しておきます。
預貯金を勝手に引き出さない
「自分は相続人なのだから、被相続人の預貯金について当然権利があるから、いつでも自由に預貯金を引き出せる」わけではないことに特に注意する必要があります。
この記事の前半で説明したように、最高裁平成28年12月19日決定が出る以前においては、預貯金は遺産分割の対象外とされていたため、相続人は自分の法定相続分については、他の相続人の同意を得ることなく、各相続人が単独で金融機関より払い戻しを受けることができたのです。
しかし、上記最高裁決定が出た以降においては、預貯金も遺産分割の対象になっています。
このため、相続人全員の合意がない状態で預貯金を引き出してはならないことをあらためて確認してください。
速やかに預貯金の口座凍結を行う
上記の「預貯金を勝手に引き出さない」を裏から支える事項です。
金融機関は、口座名義人が他界した旨の情報を得た場合、当該口座名義人の口座を凍結し、所定の手続きが完了するまでは預貯金を引き出せないようにする措置を講じます。
しかし、金融機関が口座名義人が亡くなったことを知らなければ、口座名義人のキャッシュカード・暗証番号を用いて預貯金を引き出すこと自体を完全に避けることはできません。
他の相続人が知らない間に口座名義人(被相続人)の口座から引き出しがなされてしまうと、相続人間で大きなトラブルに発展します。
こうした事態を避けるため、口座名義人が亡くなった場合には、速やかに金融機関に連絡して、口座凍結を行うことが肝要です。
遺産分割前にお金が必要な場合
個別の事案によっては、相続人において遺産分割を行う前の時点において、当面の生活費や被相続人の葬儀費用を工面する必要が出てくる場合もあり得るところです。
こうした場合に対応できるよう、遺産分割前の相続預金の払戻し制度が定められています(民法第909条の2)。
家庭裁判所の保全処分
この方法は、各相続人が他の相続人同意なしに単独で家庭裁判所に対して保全処分を申し立てることにより、預貯金の払い戻しを受けるというものです(家事事件手続法第200条第3項参照)
この制度は、上記の葬儀費用等のように急を要する出費に対応するため、ひとまず相続財産となる預貯金の払戻しを認めようとするものであると言えます。
この制度を利用するためには、相続人は遺産分割の審判・調停をともに申し立てる必要があります。
金融機関の窓口での払戻し
各相続人は、単独で金融機関の窓口において、所定の手続きに従い、預貯金の払い戻しを受けることができます。
各相続人は、相続財産としての預貯金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算により求められる金額について、審判・調停によることなく払戻しをうけることができます。
単独で払戻しができる額=相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
計算式は、上記のとおりですが、同一の金融機関から払戻しを受けることができる上限額は150万円であることに注意が必要です。
まとめ
この記事では、遺産分割における預貯金の取扱いについて解説しました。
最高裁平成28年12月19日決定により、金融機関における相続実務が変更されているため、相続人としては原則として預貯金の払戻しには、全ての相続人による遺産分割協議を必要とし、各相続人が単独で行うことはできないことに留意する必要があります。
もっとも、当面の必要資金を用意する必要に対しては、相続預金の払戻し制度があるため、これを利用することが良いでしょう。
執筆者プロフィール
- 累計1300件以上の相続相談に対応し、NHKの番組でも『遺産相続問題に詳しい弁護士』としてご紹介いただきました。相続に関する書籍も多数出版しています。難易度の高い相続案件も対応可能です。初回相談では、相談者の方のお話をじっくりお伺いし、相談者の方の立場に立って考え抜き、できるだけ簡単な言葉で分かりやすく説明することを心がけています。
最新の投稿
- 2025年7月25日コラム相続人以外の貢献も報われる!「特別寄与料」と生前対策の重要性
- 2025年7月18日コラム遺産相続の相談先どこがいい?【弁護士が徹底解説】最適な専門家選びとトラブル解決の道筋
- 2025年6月13日遺書と遺言書の違いを弁護士が徹底解説!
- 2025年5月2日【相続で介護の寄与分が認められるために必要な6つの要件とは?】判例と計算方法を弁護士が解説
その他のコラム
相続人以外の貢献も報われる!「特別寄与料」と生前対策の重要性
コラムはじめに 相続の場面では、法定相続人ではない親族が被相続人(亡くなった方)に多大な貢献をしたにもかかわらず、遺産を直接受け取ることができないという問題がありました。例えば、長年、義理の親の介護に尽くしたお嫁さんなどがこれに該当し、その献身的な貢献が報われないという不公平が生じていました。このような不公平を解消するため、2019年の民法改正で「特別寄与料」という新たな制度が創設
【相続放棄】前後にしてはいけないこと|財産処分の注意点を解説
コラム相続放棄のことで悩んでいる方は必見。この記事では相続放棄の前後にしてはいけないことや注意点について詳しく解説しています。実は知らずに行動すると、放棄の効力が認められない可能性があるのです。この記事を読めば、相続放棄前後の正しい対応方法が分かります。 「相続放棄の手続きをしたけど、故人の遺品の片付けや携帯電話を解約しても大丈夫だろうか?」と悩んでいませんか?実は相続放棄の前後にしてはいけないこ
遺産分割における預貯金の配分方法の完全解⁉
コラム相続が発生した場合には、被相続人が残した相続財産の中に銀行等の金融機関における預貯金があることが通常でしょう。 相続人が1名のみである場合はともかく、複数名の相続人がいる場合、相続財産を構成する預貯金の配分(取り分)をどのようにすればよいのでしょうか。 「誰がどれだけの配分を受けることができるのか」ということはもちろん、その配分方法も気になるところです。 ・口座を解約して預貯金を
遺産相続の相談先どこがいい?【弁護士が徹底解説】最適な専門家選びとトラブル解決の道筋
コラム「大切な家族が亡くなり、遺産相続の手続きに直面したけれど、どこに相談すればいいのか分からない…」「遺産分割で家族間の意見が食い違いそう…」「相続税がどれくらいかかるのか不安…」 遺産相続は、誰もが一度は経験する可能性がある一方で、その手続きや法律の知識は非常に複雑で、多くの方が「何から手をつければいいのか分からない」と悩みを抱えています。もし、相続人間で意見の対立があれば、精神的な負担はさら
遺留分侵害額請求されたら?いきなり請求された時の適切な対応手順!
コラム相続トラブルをできるだけ起こりにくくしてくれるのが「遺言書」です。 ところが遺言書によっては偏った分け方が原因で、受け取り分が少ないと感じる相続人が出てくることもあります。 すると遺産の大半を受け取った相続人に対し、自分たちが正当に受け取れるであろう遺産を請求してくる可能性が考えられます。 これを「遺留分侵害額請求」といいます。 では、このような時一体どうすればよいのでしょ
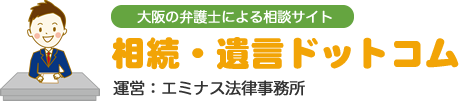
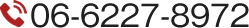




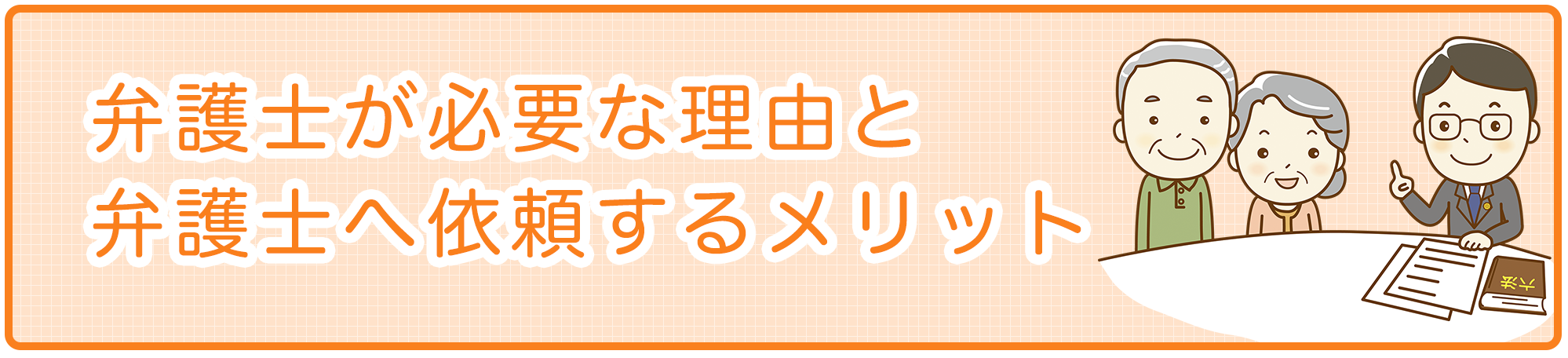
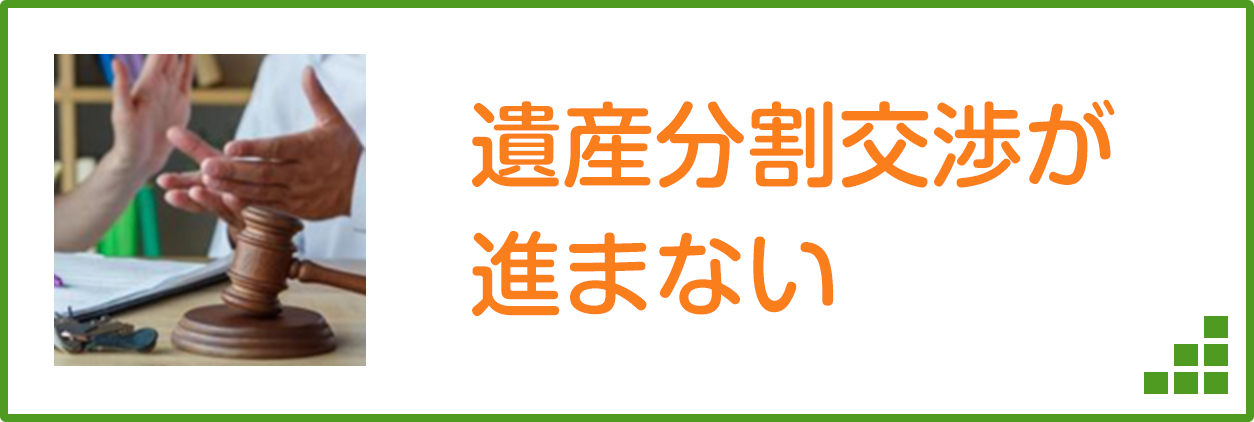

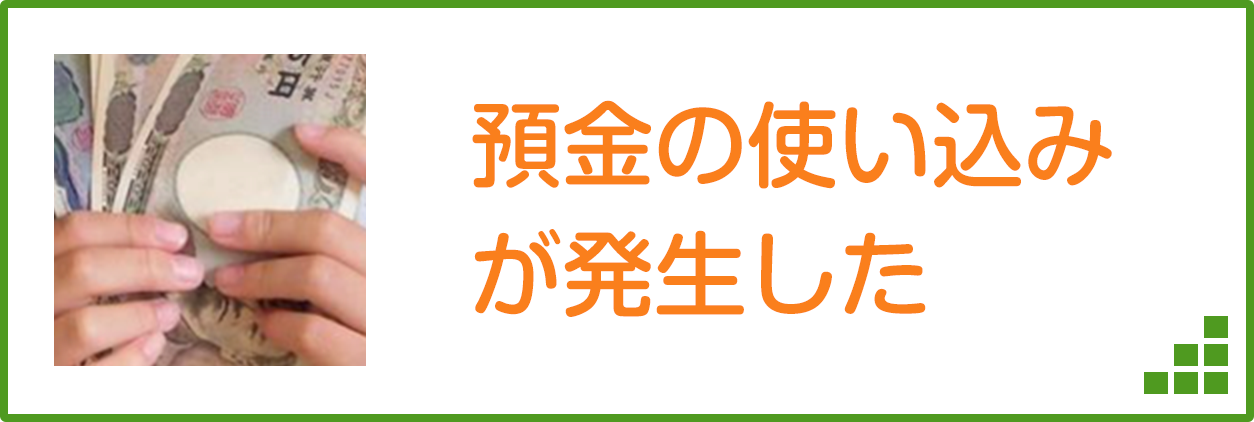

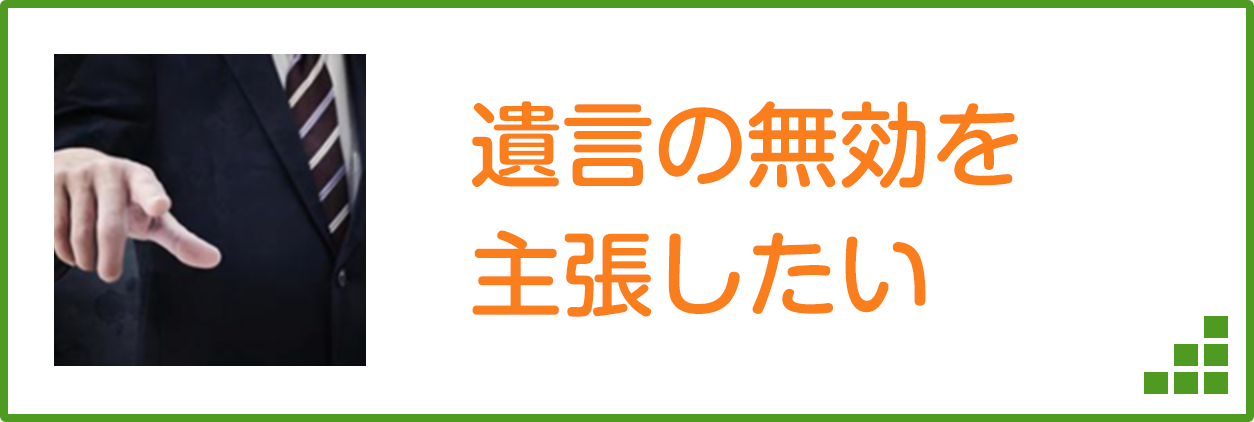
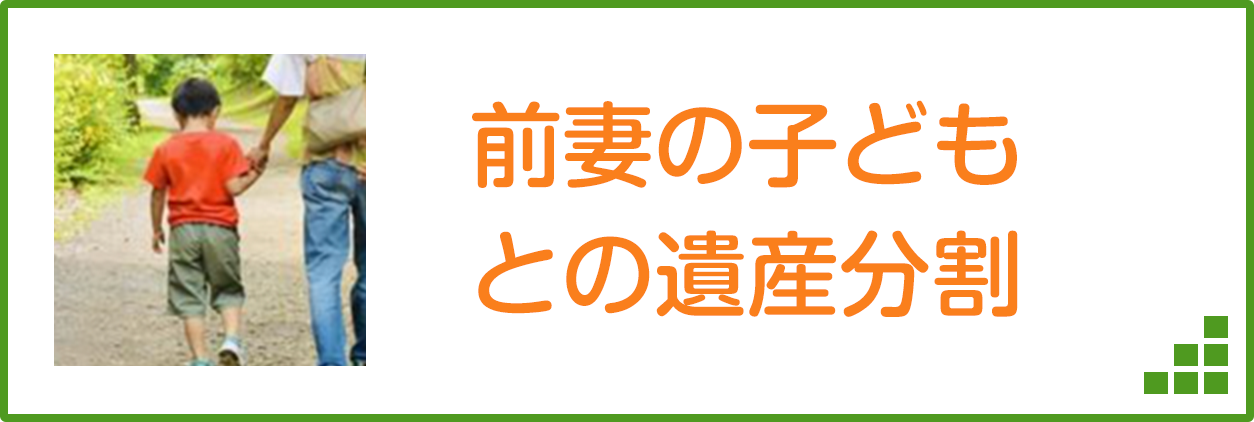
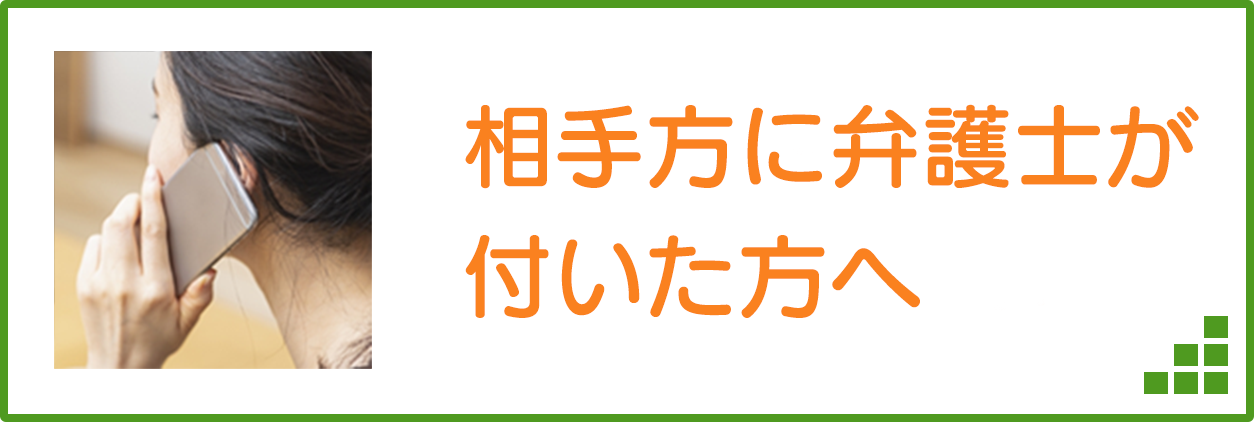
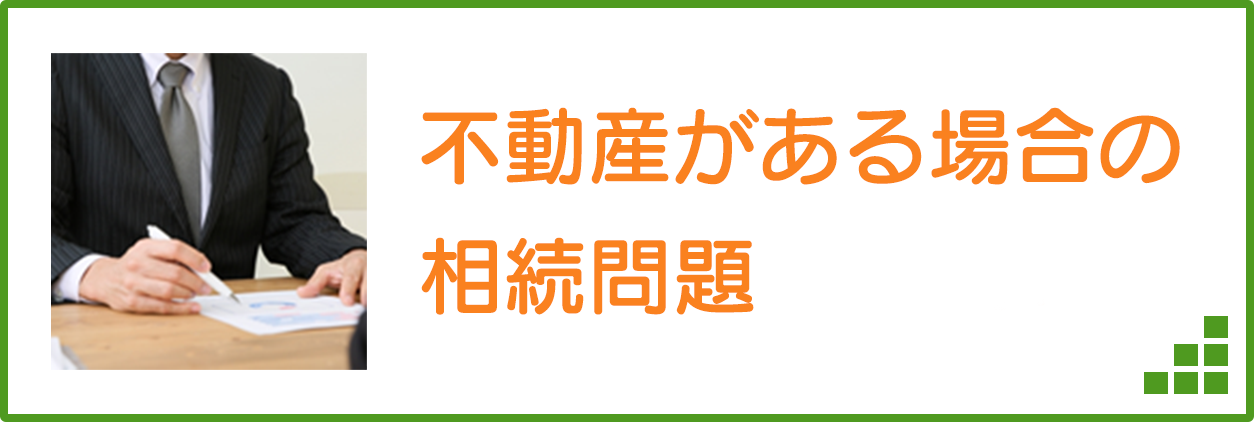


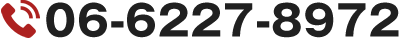






代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
リーガルサービスの提供を通じてお客様を笑顔にしたいとの思いから事務所名を「エミナス法律事務所」(笑みを為す)としました。
お客様を笑顔にするためには、出来るかぎりご希望に沿ったベストな解決を図る必要があります。
ご希望に沿ったベストな解決を図るためには、お客様のお話をじっくりと丁寧にお聞きすることが何より大切です。
そのため、当事務所では、十分なお時間を取り、まずは、お客様が抱いておられるご不安や紛争の解決方法に関するご希望を正確に理解するよう努めています。
その上で、ご不安を解消あるいは低減できるよう、ご納得いただけるまで何度でもお答えさせていただくとともに、どこまでもお客様に寄り添い、笑顔になれる解決を全力でサポートいたします。