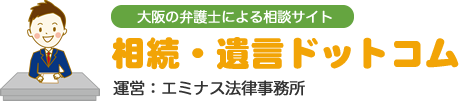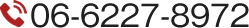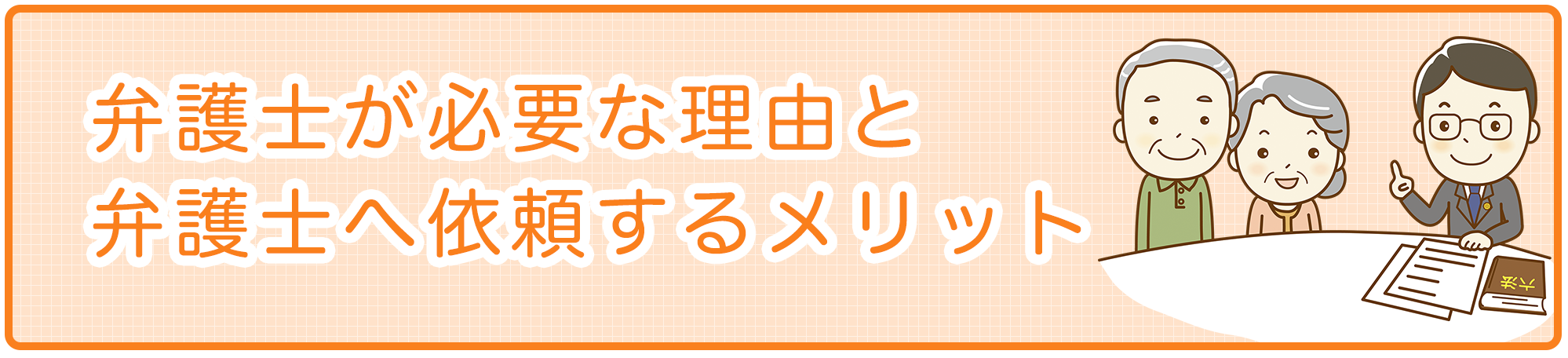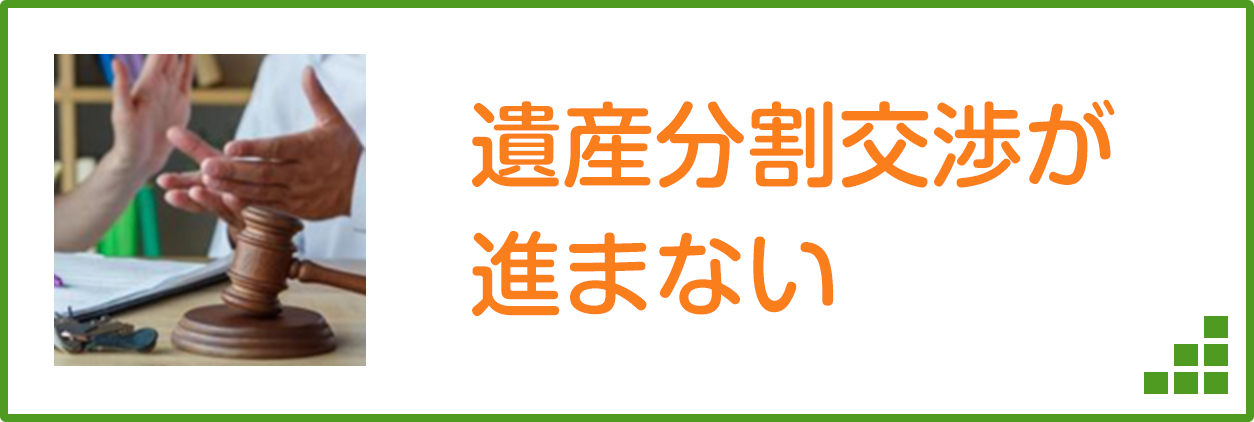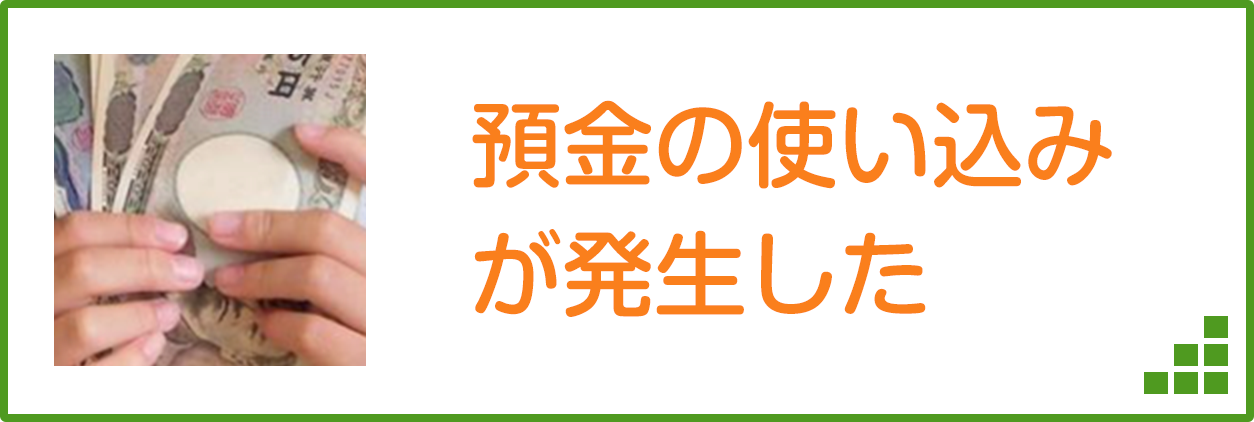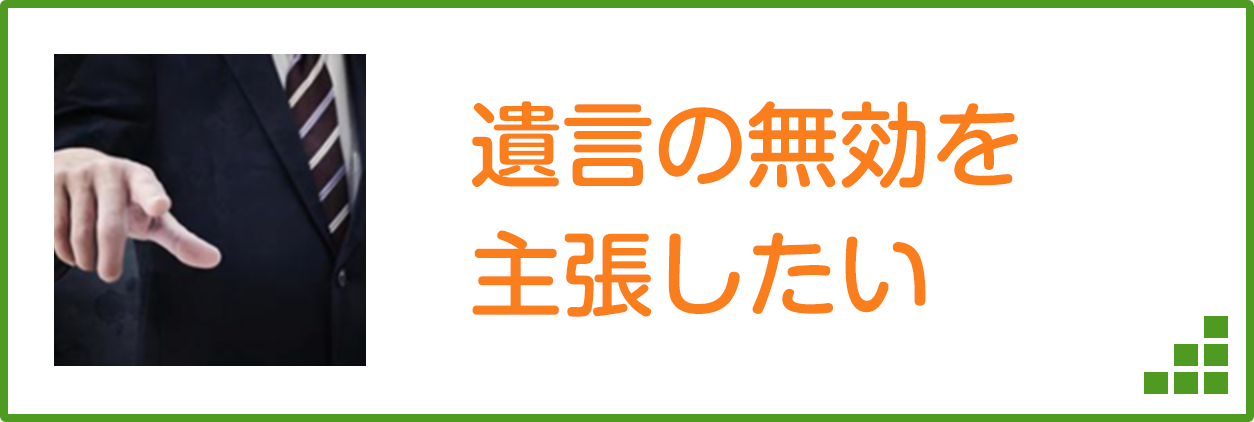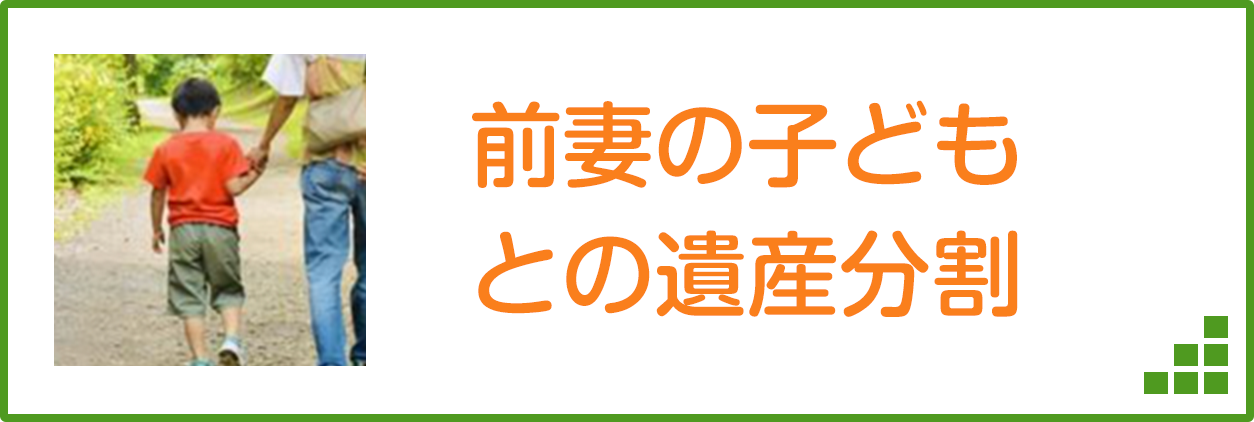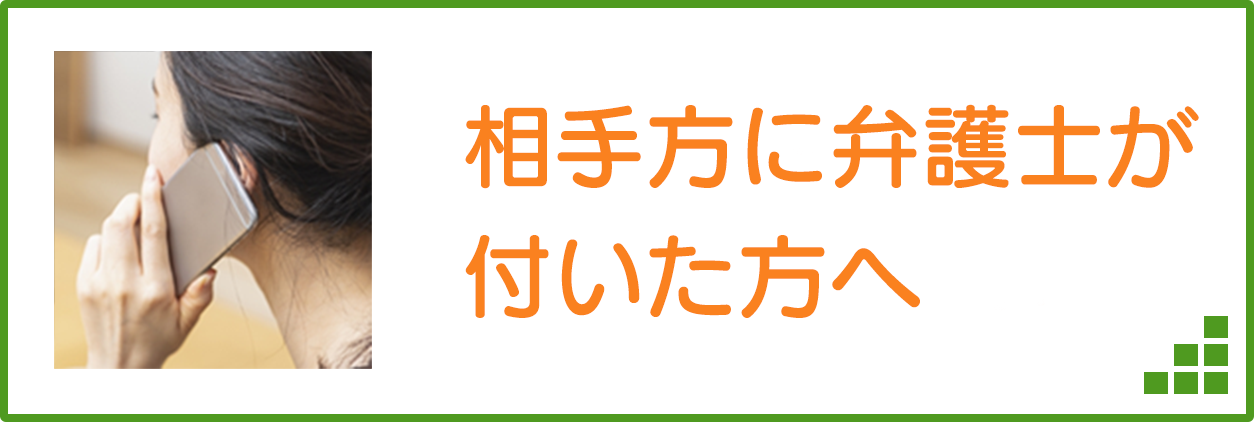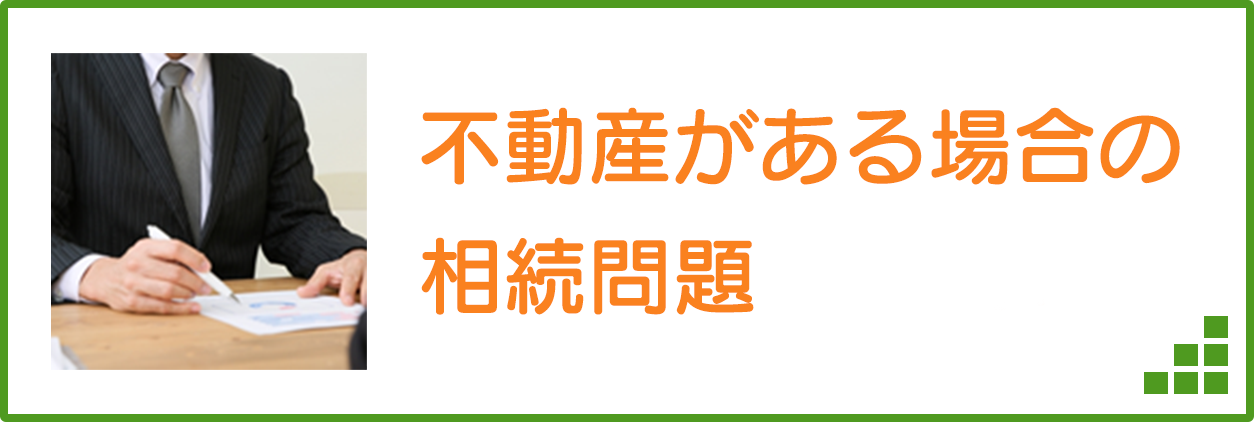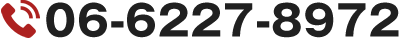相続人以外の貢献も報われる!「特別寄与料」と生前対策の重要性
コラム目次
はじめに
相続の場面では、法定相続人ではない親族が被相続人(亡くなった方)に多大な貢献をしたにもかかわらず、遺産を直接受け取ることができないという問題がありました。例えば、長年、義理の親の介護に尽くしたお嫁さんなどがこれに該当し、その献身的な貢献が報われないという不公平が生じていました。このような不公平を解消するため、2019年の民法改正で「特別寄与料」という新たな制度が創設されました。本記事では、この特別寄与料を中心に、相続人以外の貢献がどのように評価され、報われるのか、また、生前にできる対策について詳しく解説します。
1. 相続人ではない親族の貢献を報いる「特別寄与料」
従来、たとえ被相続人の介護に大きく貢献した親族がいても、その人が法定相続人に該当しない場合(例:長男の妻、嫁いだ娘の夫、孫の配偶者など)は、遺産を直接受け取ることができませんでした。相続人以外の貢献者には遺産を分配できない制度上の限界があったのです。
ただし、改正前の制度においても、相続人以外の親族(例えば長男の妻)による貢献に報いるべく、相続人である夫(長男)の「履行補助者」として行われたものと評価して、夫の寄与分として認めるという救済理論がありました。しかし、このような理論では、代襲相続なくして相続人である夫が先に死亡していたような場合には、妻が救済されないなどの限界がありました。
このような状況での不公平を制度的に解消するため、2019年の民法改正により新たに「特別寄与料」という仕組みが創設されました。
特別寄与料とは、相続人でない親族が被相続人に対し介護や看護など特別の貢献をした場合に、その労に報いるため相続人に金銭を請求できる制度です。
1.1. 特別寄与料を請求できる人
特別寄与料を請求できるのは、「相続人以外の親族」に限られます。具体的には、被相続人の6親等内の血族(甥姪・いとこまで)および3親等内の姻族(義理の両親・義兄弟姉妹・嫁婿など)が該当します。ただし、内縁の妻・夫、事実婚のパートナーなど、法律上の親族に当たらない方はこの制度を利用できません。
1.2. 特別寄与料が認められる条件
特別寄与料が認められるためには、以下の4つの条件を全て満たす必要があります。
1. 無償での療養看護その他の労務提供
被相続人に対し、無償で介護・看護(療養看護)を行ったこと、または家業の手伝いなどの労務を提供したこと。金銭による支援は含まれません。
2. 被相続人の財産の維持または増加
上記の労務提供によって、被相続人の財産が減少するのを防いだ(維持)か、または財産が増加したと評価できること。
3. 労務提供と財産維持・増加の因果関係
提供された労務(①)と、被相続人の財産の維持または増加(②)との間に直接的な因果関係があること。
4. 「特別の寄与」であること
相続人以外の親族には法定相続分がなく、原則として遺産を受け取る権利がないため、この「特別の寄与」の解釈は、寄与分制度におけるそれとは異なります。特別寄与料制度の趣旨が、相続人ではない親族の顕著な貢献によって生じる不公平を是正することにあるため、その貢献に金銭的に報いることが不公平を是正するために必要かつ相当であると認められる程度の顕著な貢献があったことを意味します。
例えば、長期間にわたり重度の要介護状態の被相続人に対し、献身的に介護・看護を行い、その結果、高額な医療費や介護費用の出費を大幅に抑えることができた場合などが「特別の寄与」として認められる典型例です。
これらの「特別の寄与」の有無や程度は、具体的な状況に応じて家庭裁判所が判断するため、客観的な証拠(介護日誌、医療記録、事業の帳簿など)が非常に重要になります。
1.3. 特別寄与料の額
特別寄与料の具体的な金額は、特別寄与者の貢献の内容や程度に応じて家庭裁判所が判断しますが、特に療養看護型の特別寄与料については、寄与分における以下の考え方が参考になります。
寄与分においては、介護による寄与分額の計算は以下の要素を考慮します。
介護報酬額(要介護度に応じた金額): 専門の介護サービスを利用した場合にかかる費用を参考にします。
介護日数(実際の介護期間): 実際に介護を行った日数を計上します。
裁量的割合: 専門家ではない親族による介護であることなどを考慮し、金額を調整する割合です。
これらを掛け合わせて算出し、一般的には「介護報酬額 × 介護日数 × 裁量割合」の形で計算されます。この裁量割合は、通常、0.5から0.8程度の間で事案に応じて適宜修正されますが、0.7あたりが平均的な数値と言われています。
1.4. 特別寄与料の請求の相手方と請求できる範囲
特別寄与料は、相続開始後に特別寄与者(寄与した親族)が相続人に対し金銭の支払いを請求することで実現します。
この請求は、各相続人に対して、その相続人が受けた「相続分の割合」(法定相続分または遺言による指定相続分)に応じて行うことになります。例えば、相続人が複数いる場合、特別寄与者は、各相続人が承継する(法定または指定)相続分の割合に応じて、それぞれの相続人に特別寄与料の負担を求めます。そのため、特定の相続人一人に対して、特別寄与料の全額を請求することはできません。
1.5. 特別寄与料を請求する場合の手続きの流れ
特別寄与料を請求する際の手続きは、以下のようになります。
1. 相続人との協議(話し合い)
まずは当事者間の話し合いで寄与料の支払いを求めます。
2. 家庭裁判所への調停申立て
協議がまとまらない場合、または協議をすることができない場合、特別寄与者は家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分の調停」を申し立てる必要があります。
3. 審判
調停でも合意できなければ審判手続に移行し、裁判官が寄与料額を判断します。
1.6. 特別寄与料の請求期限
特別寄与料の請求権には厳格な期間制限があり、以下のいずれかの期限内に、家庭裁判所へ「特別の寄与に関する処分の調停」を申し立てる必要があります。
相続開始および相続人を知ったときから6か月以内
相続開始の時から1年以内
この期間を過ぎると、特別寄与料を請求する権利は消滅します。この期間制限は非常に短いため、相続開始後は速やかに弁護士等の専門家に相談し、必要な手続を進める必要があります。
なお、特別寄与料として受け取った金銭は、税法上被相続人からの遺贈とみなされ、相続税の課税対象となる点に注意が必要です(法定相続人以外の遺産取得となるため、相続税額が2割加算されます)。
2. 「寄与分」と「特別寄与料」の違い
同じ「貢献に応じた見返りを受け取る制度」でも、両者は目的や対象者が異なります。
2.1. 相続人の貢献を評価する「寄与分」とは
相続における「寄与分」とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人がいる場合に、その相続人の遺産取得分を増やすことができる制度です。法定相続分だけでは貢献度が考慮されないため、介護や家業手伝い、金銭援助などで他の相続人よりも財産に寄与したケースでの不公平を解消する目的があります。例えば、生前に親の介護を無償で長年続けた子どもがいる場合、遺産分割の際に寄与分を主張することで、他の相続人より多くの遺産を受け取れる可能性があります。
寄与分の典型的な例としては、以下のケースが挙げられます。
介護・看護型(療養看護型)
同居の親の介護・看護を長期間にわたり無償で行い、介護費用の支出を減らした場合。例:長女が10年間にわたり要介護状態の母親の世話をして、施設利用費を節約できたケース。
家業従事型
家業を無報酬で手伝い、本来であれば必要な給与の支払いを免れていた場合。例:長男が父親の経営する商店を無給で手伝っていたケース。
金銭出資型
被相続人に対し事業資金を援助し、その財産減少を防いだ場合。例:次女が父親が営む事業のために金銭を贈与した結果、親の預貯金が減らずに済んだケース。
2.2. 特別寄与料との比較
寄与分と特別寄与料には以下のような違いがあります。
請求できる人の範囲
寄与分は法定相続人のみが主張可能ですが、特別寄与料は法定相続人以外の親族が主張できます。
寄与行為の種類
寄与分は金銭援助、療養看護、家業手伝いなど幅広く評価対象となります。一方、特別寄与料は労務提供による貢献のみが対象で、財産提供型の貢献は考慮されません。
効果(受け取れるもの)
寄与分は遺産分割において寄与者の相続分自体を増加させる制度です。特別寄与料は寄与者に認められる金銭請求権であり、寄与者自身は遺産分割に加わりません。
手続方法と期限
寄与分は遺産分割協議の場で主張し、相続開始後10年以内に主張可能です。特別寄与料は相続発生後に家庭裁判所への調停申立てが必要となり、請求期間は相続開始後6か月以内かつ1年以内と非常に短いです。
3. 相続人以外の親族に財産を遺すための生前対策
特別寄与料は相続開始後に金銭請求する方法ですが、そもそも被相続人が生前の対策によって相続人以外の貢献者に財産を渡すことも可能です。特別寄与料は相続人との協議が必要でトラブルになりやすい面もあるため、確実に貢献者へ財産を遺したい場合は以下のような方法も検討すると良いでしょう。
遺言による遺贈
遺言書を作成し、相続人以外の人にも特定の財産や金額を遺贈(遺言による贈与)する方法です。遺言で受け取れる財産を指定しておけば、相続人でない介護者にも遺産を遺すことができます。ただし遺留分を侵害すると無効部分が生じ得るため、内容には注意が必要です。
養子縁組
貢献者を養子にして法定相続人にしてしまう方法です。法律上の親子関係を築けば、その方は相続人として寄与分を主張することも可能になります。
生前贈与
被相続人が存命中に貢献者へ財産を贈与しておく方法です。年間110万円以内であれば贈与税が非課税となる枠があります。
生命保険を活用
被相続人を契約者・被保険者とし、貢献者を保険金受取人に指定しておけば、その人は相続人でなくとも生命保険金を受け取れます。生命保険金は受取人固有の財産となり、基本的に遺産分割の対象外です。
これらの方法を組み合わせれば、相続人以外であっても生前に一定の財産を確実に受け取れるよう手当てすることが可能です。
4. まとめ:特別寄与料の活用と専門家への相談
法定相続人ではない親族の貢献を金銭的に評価する「特別寄与料」制度は、2019年の法改正により、これまで報われることのなかった献身的な介護などに対する不公平を是正するために創設されました。 しかし、その請求には「特別の寄与」であることの立証や、相続人との協議、家庭裁判所での手続きが必要となるため、手続きの煩雑さや他の相続人との対立が生じる可能性も少なくありません。特に、請求できる期間が相続開始から6か月または1年と非常に短く、この期間を過ぎると権利が消滅してしまう点には注意が必要です。適正な特別寄与料の算定や、貢献の事実を証明するための証拠集めは非常に専門的な知識を要します。
相続で特別寄与料に関する問題が発生した際は、ぜひ相続に強い弁護士へご相談ください。当事務所でも遺産相続に関するご相談を承っており、相続に強い弁護士が状況を丁寧にお伺いし、依頼者様の正当な権利を守るため最善のアドバイスと対応策をご提案いたします。円満な解決のためにも、どうぞお気軽にお問い合わせください。
執筆者プロフィール
- 累計1300件以上の相続相談に対応し、NHKの番組でも『遺産相続問題に詳しい弁護士』としてご紹介いただきました。相続に関する書籍も多数出版しています。難易度の高い相続案件も対応可能です。初回相談では、相談者の方のお話をじっくりお伺いし、相談者の方の立場に立って考え抜き、できるだけ簡単な言葉で分かりやすく説明することを心がけています。
最新の投稿
- 2025年7月25日コラム相続人以外の貢献も報われる!「特別寄与料」と生前対策の重要性
- 2025年7月18日コラム遺産相続の相談先どこがいい?【弁護士が徹底解説】最適な専門家選びとトラブル解決の道筋
- 2025年6月13日遺書と遺言書の違いを弁護士が徹底解説!
- 2025年5月2日【相続で介護の寄与分が認められるために必要な6つの要件とは?】判例と計算方法を弁護士が解説
その他のコラム
遺産分割における預貯金の配分方法の完全解⁉
コラム相続が発生した場合には、被相続人が残した相続財産の中に銀行等の金融機関における預貯金があることが通常でしょう。 相続人が1名のみである場合はともかく、複数名の相続人がいる場合、相続財産を構成する預貯金の配分(取り分)をどのようにすればよいのでしょうか。 「誰がどれだけの配分を受けることができるのか」ということはもちろん、その配分方法も気になるところです。 ・口座を解約して預貯金を
【相続放棄】前後にしてはいけないこと|財産処分の注意点を解説
コラム相続放棄のことで悩んでいる方は必見。この記事では相続放棄の前後にしてはいけないことや注意点について詳しく解説しています。実は知らずに行動すると、放棄の効力が認められない可能性があるのです。この記事を読めば、相続放棄前後の正しい対応方法が分かります。 「相続放棄の手続きをしたけど、故人の遺品の片付けや携帯電話を解約しても大丈夫だろうか?」と悩んでいませんか?実は相続放棄の前後にしてはいけないこ
遺留分侵害額請求されたら?いきなり請求された時の適切な対応手順!
コラム相続トラブルをできるだけ起こりにくくしてくれるのが「遺言書」です。 ところが遺言書によっては偏った分け方が原因で、受け取り分が少ないと感じる相続人が出てくることもあります。 すると遺産の大半を受け取った相続人に対し、自分たちが正当に受け取れるであろう遺産を請求してくる可能性が考えられます。 これを「遺留分侵害額請求」といいます。 では、このような時一体どうすればよいのでしょ
相続人以外の貢献も報われる!「特別寄与料」と生前対策の重要性
コラムはじめに 相続の場面では、法定相続人ではない親族が被相続人(亡くなった方)に多大な貢献をしたにもかかわらず、遺産を直接受け取ることができないという問題がありました。例えば、長年、義理の親の介護に尽くしたお嫁さんなどがこれに該当し、その献身的な貢献が報われないという不公平が生じていました。このような不公平を解消するため、2019年の民法改正で「特別寄与料」という新たな制度が創設
遺産相続の相談先どこがいい?【弁護士が徹底解説】最適な専門家選びとトラブル解決の道筋
コラム「大切な家族が亡くなり、遺産相続の手続きに直面したけれど、どこに相談すればいいのか分からない…」「遺産分割で家族間の意見が食い違いそう…」「相続税がどれくらいかかるのか不安…」 遺産相続は、誰もが一度は経験する可能性がある一方で、その手続きや法律の知識は非常に複雑で、多くの方が「何から手をつければいいのか分からない」と悩みを抱えています。もし、相続人間で意見の対立があれば、精神的な負担はさら