【相続で介護の寄与分が認められるために必要な6つの要件とは?】判例と計算方法を弁護士が解説
目次
「相続で介護の寄与分が認められるだろうか?」と心配の方は必見!この記事では相続で介護の寄与分が認められるために必要な6つの要件、介護が相続時の寄与分として認められにくい2つの理由、相続時に介護の寄与分を認めてもらうのに必要な2つの証拠資料、寄与分の計算方法を解説します。
「長年にわたり親の介護を一手に引き受けてきたのに、遺産分割で適切に評価されないのでは」と懸念を抱えていませんか?介護による相続の寄与分は、単なる同居や日常的な世話だけでは認められないケースが大半です。
法的に評価される介護の寄与分には、厳格な立証責任と具体的な要件を満たすことが求められます。多くの方が困難に直面する現実です。
本記事では、相続における介護の寄与分が認定される条件や具体的な算定方法、重要判例を解説します。
この記事を読むことで、なぜ介護の寄与分が簡単に認められないのか、その背景と対策が明確になるでしょう。相続と介護の寄与分をめぐる問題に直面している方は、ぜひ最後までご覧ください。
寄与分とは│特別な貢献をした相続人が法定相続分を超える財産を相続できる制度
遺産相続において、通常は法律で定められた割合(法定相続分)に従って分配が行われますが、この原則に例外をもたらす制度が「寄与分」です。
民法第904条の2に規定された寄与分は、被相続人の資産形成や維持に特別の寄与をした相続人を評価する仕組みとなっています。
親の事業を無償で長年手伝い続けた子や、自身のキャリアを犠牲にして献身的にな療養介護をした相続人などが典型的な例です。
特に介護の寄与分については、判断基準が複雑で争いになりやすい性質を持っています。寄与分の金額を決定する流れは、まず相続人の間の協議からスタートします。
話し合いが物別れに終わった場合には、家庭裁判所での調停、さらには審判へと進まざるを得ません。注意すべきは請求権者の範囲で、相続人のみが寄与分を請求できる点です。
相続で介護の寄与分が認められる6つの要件
遺産分割における介護の寄与分認定には、明確な基準が存在します。裁判例や実務から導き出された主要な判断材料は以下の6点です。
「療養介護の必要性」「通常の扶養を超える特別な貢献」「継続性」「無償性」「専従性」「財産の維持・増加への貢献」
全ての条件を満たして初めて、介護による寄与分が法的に評価されます。各要件についてのより詳細な解説は、これに続く各項目で順に検討していきます。
判断基準を把握することで、自分のケースが寄与分として認められる可能性を適切に評価できるでしょう。
①被相続人が療養介護を必要とする状態であったこと
相続の際に介護の寄与分が認められるには、被相続人が日常生活を送る上で、療養介護を必要とする状態であったことが挙げられます。
寄与分として評価されるのは、脳梗塞により半身不随となり自力での生活が困難な状態や、認知症が進行したことを知って見守りが必須な状況などです。
判断基準として、被相続人が「要介護2」以上の認定を受けていたことが1つの目安です。
一方で、被相続人が介護施設に入所していて、定期的にお見舞いに通う程度では、寄与分として認められません。通院の付き添いだけでは、必要不可欠な介護とは見なされないケースがほとんどです。
②扶養の範囲を超えた特別な貢献
介護による寄与分が認められるには、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献が必須です。要介護度が高く施設入所が適切な状態にもかかわらず、自宅で排せつ介助や入浴支援を継続した場合、裁判例では限度内において「特別の寄与」と認定される傾向があります。
上記のような貢献が被相続人の財産維持に直接寄与したと認められた場合に限り、寄与分が認められます。
③継続性
遺産分割時に介護の寄与分を主張する上で、「継続性」という時間的要素は極めて重要です。裁判所は一時的な支援ではなく、長期にわたる献身的な介護行為を高く評価する傾向にあります。
例えば「年末年始だけ帰省して世話をした」「入院時の数週間のみ付き添った」といった短期間の介護では、寄与分としての評価は難しいでしょう。裁判例からは、少なくとも「相当期間」の継続的介護が必要とされています。
具体的な期間については明確な基準はなく、ケースバイケースで判断されます。介護頻度や被介護者の状態、他の相続人の状況などが総合的に考慮されるのが実情です。
実務上は、数年以上の長期間にわたる日常的な介護ケースほど寄与分として認められやすくなる傾向が見られます。相続で介護の寄与分を主張する際は、この「時間的継続性」の立証が不可欠なポイントとなるでしょう。
④無償性
寄与分が認められるためには、療養介護を無償で行っていたことが条件です。報酬や金銭的な対価を受け取っていた場合、寄与分として認められません。
「不動産を譲り受けた」「生活費全般を被相続人の財産で賄っていた」などの事実があると、無償とは主張できません。
「お礼として他の相続人よりも多額の贈与を受けた」といったケースも同様です。寄与分を主張する際には、対価を受け取っていないことを証明できる資料や記録を保管しておきましょう。
⑤専従性
相続における介護の寄与分が認められるためには、介護行為が片手間の世話ではなく、相当量の時間と労力を費やした「特別な負担」になることです。「専業」や「専念」ということまで求められるわけではありませんが、日常生活に大きな影響を与えるほどの負担があったかどうかが、寄与分の評価において重視されます。
被相続人の介護のために「仕事を退職した」「休職期間を取得した」など、自身のキャリアや収入に影響するような選択をしていた場合は、寄与分として認められる可能性が高くなります。
自分の生活リズムや家族との時間を大幅に犠牲にするような形で介護に従事していた事実があるならば、寄与分の評価において考慮される要素になるでしょう。
⑥被相続人の財産維持や増加への貢献
介護による寄与分が認められるための条件として、その介護行為が被相続人の資産保全や増加に実質的に寄与したことが挙げられます。
具体的には、自宅での献身的な介護によって「施設入所費用」や「専門介護人材の雇用費」など、年間数百万円の支出を回避できたことを立証できれば、寄与分として評価される可能性が高まるでしょう。
裁判所は、介護行為と財産保全の因果関係を重視します。例えば、在宅介護により特別養護老人ホームへの入所が不要となった場合、月額15〜30万円程度の施設費用が節約できたと算定されることがあります。
寄与分の審査では「仮に介護をしなかったら、どれほどの財産が減少していたか」という視点で判断されるため、経済的な貢献を数値で示すことです。単に介護したという事実だけでは、財産への貢献という要件を満たせない点に注意が必要です。
介護が相続時の寄与分として認められにくい2つの理由
相続における介護の寄与分が認められるケースは実際には限られています。その背景には主に2つの障壁があります。まず、厳格な法的要件を充足することの難しさです。
次に、介護の実態を裏付ける証拠の確保が容易でないという現実です。これらが相まって、介護に対する寄与分の認定は狭き門となっています。以下では、この2つの課題について詳細に検討していきます。
①寄与分の要件を満たすのが困難
寄与分の要件を満たすことは、実際にはかなり難しい場合が多いです。
まず、寄与分の基本的な考え方として「特別な貢献」が必要です。親の介護をしていたという事実だけでは、法律上の寄与分として認められないでしょう。
特に問題となるのは「特別な貢献であるか」という要件です。民法では親子間に扶養義務が存在するため、この義務を超える程度の介護が行われていなければ寄与分は認められません。
寄与分が認められるためには、長期間にわたる献身的な介護や、特別な医療的ケアの提供などが必要です。
厳格な基準があるため、多くの相続人が感じている「介護の苦労」が、法的に評価される「寄与分」として認められるには高いハードルがあります。
②証拠資料の収集が困難
寄与分が認められにくい理由の1つに、証拠資料の収集の難しさが挙げられます。寄与分を主張するには、被相続人の財産維持や増加に貢献したことを証明する具体的な資料が必要です。
しかし、多くの場合には介護や支援する中で証拠を意識して記録を残す人は少なく、結果として寄与分が認められないケースが多発しています。
介護にかかった時間や内容を示す記録、領収書などが不十分だと、裁判所に寄与行為の実態を認めてもらうことは困難です。
介護を始めた段階から日々の記録や関連資料を整理しておきましょう。証拠不足によるトラブルを防ぐためにも、早い段階で専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
相続時に介護の寄与分を認めてもらうのに必要な2つの証拠資料
寄与分を認めてもらうには、以下の証拠を準備しましょう。
①介護認定資料や医師の診断書
• 被相続人の介護状態を客観的に示す書類
• 公的な「介護保険資格者証」が有効
• 要介護認定がない場合は医師の診断書で代替可能
②介護した事実を証明する記録
• 日々の介護内容を記した介護日誌
• 食事・入浴・排せつ介助などの具体的内容
• 実施日、介護日数、時間、医療ケア内容など
これらは「扶養義務を超えた特別な貢献」を証明する資料となります。
寄与分の計算方法
介護による寄与分の計算は以下の要素を考慮します。
• 介護報酬額(要介護度に応じた金額)
• 介護日数(実際の介護期間)
• 裁量割合
これらを掛け合わせて算出し、介護報酬額×介護日数×裁量割合(通常、0.5から0.8程度の間で事案に応じて適宜修正されますが、0.7あたりが平均的な数値と言われています。)が目安です。
他にも家事従事型や財産管理型など、ケースに応じた計算方法があります。具体的な計算には専門家の助言が必要です。
以下が寄与分の相続分への反映方法です。
寄与者の相続分 = (遺産総額-寄与分)×法定相続分+寄与分
他の相続人の相続分 = (遺産総額-寄与分)×法定相続分
まとめ
介護の寄与分が認められるには次の要件を満たす必要があります。
• 療養介護の必要性
• 通常の扶養を超える特別な貢献
• 療養介護の継続性
• 無償性
• 専従性
• 財産維持・増加への貢献
寄与分の主張には適切な証拠と手続きが必要です。トラブル回避や複雑なケースでは、弁護士への早めの相談をおすすめします。
執筆者プロフィール
- 累計1300件以上の相続相談に対応し、NHKの番組でも『遺産相続問題に詳しい弁護士』としてご紹介いただきました。相続に関する書籍も多数出版しています。難易度の高い相続案件も対応可能です。初回相談では、相談者の方のお話をじっくりお伺いし、相談者の方の立場に立って考え抜き、できるだけ簡単な言葉で分かりやすく説明することを心がけています。
最新の投稿
- 2025年7月25日コラム相続人以外の貢献も報われる!「特別寄与料」と生前対策の重要性
- 2025年7月18日コラム遺産相続の相談先どこがいい?【弁護士が徹底解説】最適な専門家選びとトラブル解決の道筋
- 2025年6月13日遺書と遺言書の違いを弁護士が徹底解説!
- 2025年5月2日【相続で介護の寄与分が認められるために必要な6つの要件とは?】判例と計算方法を弁護士が解説
その他のコラム
遺書と遺言書の違いを弁護士が徹底解説!
遺書と遺言書の違いを弁護士が徹底解説! 「遺書」と「遺言書」。どちらも亡くなった方が生前に自身の想いや財産について書き残すもの、という漠然としたイメージをお持ちかもしれません。しかし、これら二つの書面は全くの別物であり、その違いを知っているかどうかが極めて重要になります。 本記事では、相続に強い弁護士が、「遺書」と「遺言書」の違いを明確にし、それぞれの法的効力、後悔しない相続を実現するた
葬式費用は誰が負担しなければならないのか?
相続・遺言Q&A葬儀費用の負担者については、法律の定めも、最高裁判所の裁判例もありませんが、実務上は、きちんと明細等を開示して説明すれば、他の相続人が葬儀費用を遺産から支出することについて異議を唱えることはあまりないと思われます。 ただ、他の相続人が異議を唱えた場合、葬儀費用を誰が負担すべきかについては、 ①喪主が負担すべきとする説(=喪主負担説) ②相続人が負担すべきとする説(
認知症の父が作成した公正証書遺言を無効にできますか?
相続・遺言Q&A無効にできる場合があります。 遺言が無効となる理由はいくつかありますが、代表的な理由は以下の3つです。 ① 遺言書が民法所定の方式に違反している場合 ② 遺言者に遺言能力がなかった場合 ③ 遺言書が偽造された場合 認知症の方が作成された遺言書の無効理由としては、まずは②の遺言能力の有無を検討することになりますが、遺言能力の有無の判断
不動産相続の名義変更に期限はある?不動産を相続したときに知っておくべき基礎知識とは?
相続により、不動産を取得したときに必ず行わなければいけないこと。それが、名義変更です。名義変更をしないままの状態が続くと、後々トラブルが発生する危険性があるので注意しなければいけません。 また、トラブルが発生する危険性以外にも知っておかなければいけない情報があります。それが、法改正による義務化です。法改正により2024年4月1日から相続により取得した不動産の名義変更が義務化されました。これに
【相続放棄】前後にしてはいけないこと|財産処分の注意点を解説
コラム相続放棄のことで悩んでいる方は必見。この記事では相続放棄の前後にしてはいけないことや注意点について詳しく解説しています。実は知らずに行動すると、放棄の効力が認められない可能性があるのです。この記事を読めば、相続放棄前後の正しい対応方法が分かります。 「相続放棄の手続きをしたけど、故人の遺品の片付けや携帯電話を解約しても大丈夫だろうか?」と悩んでいませんか?実は相続放棄の前後にしてはいけないこ
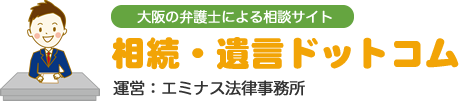
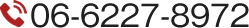



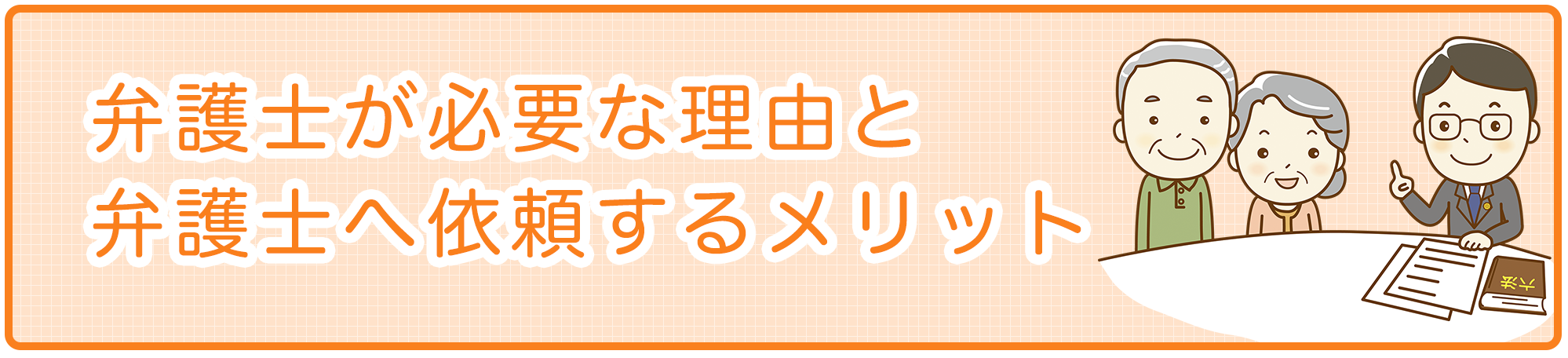
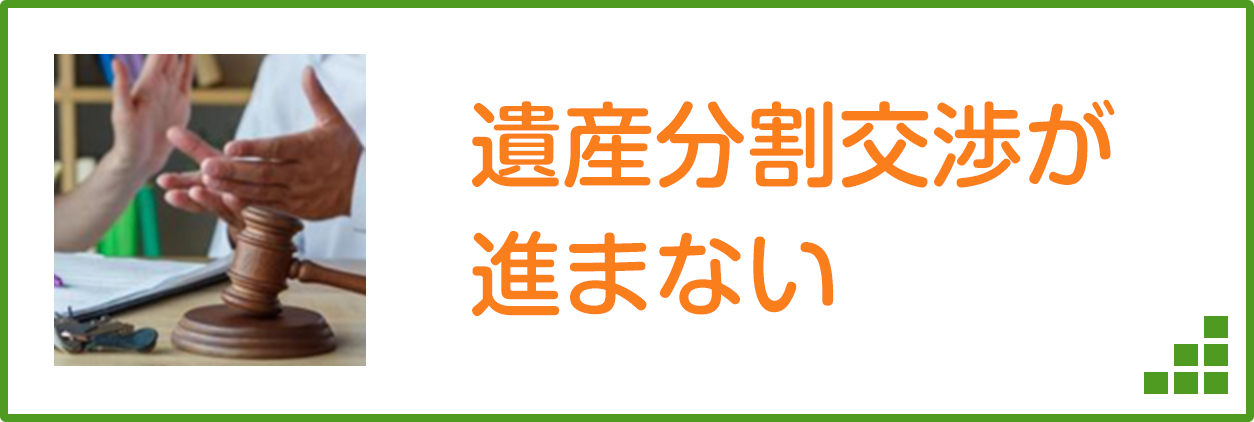

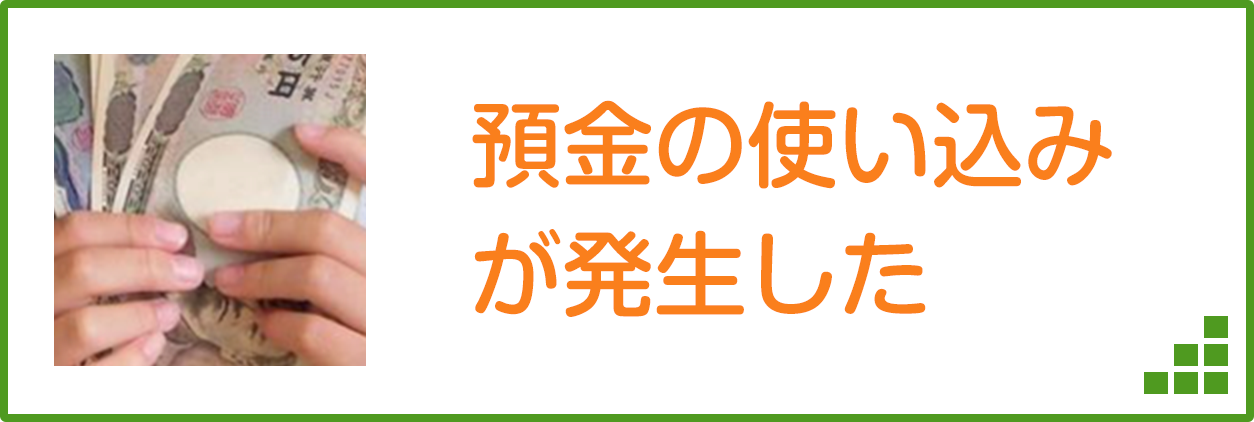

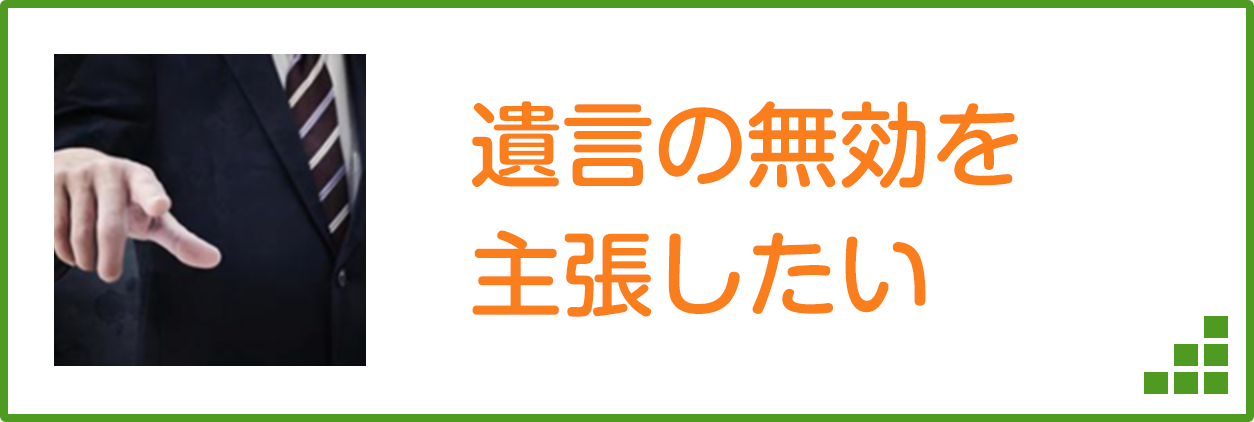
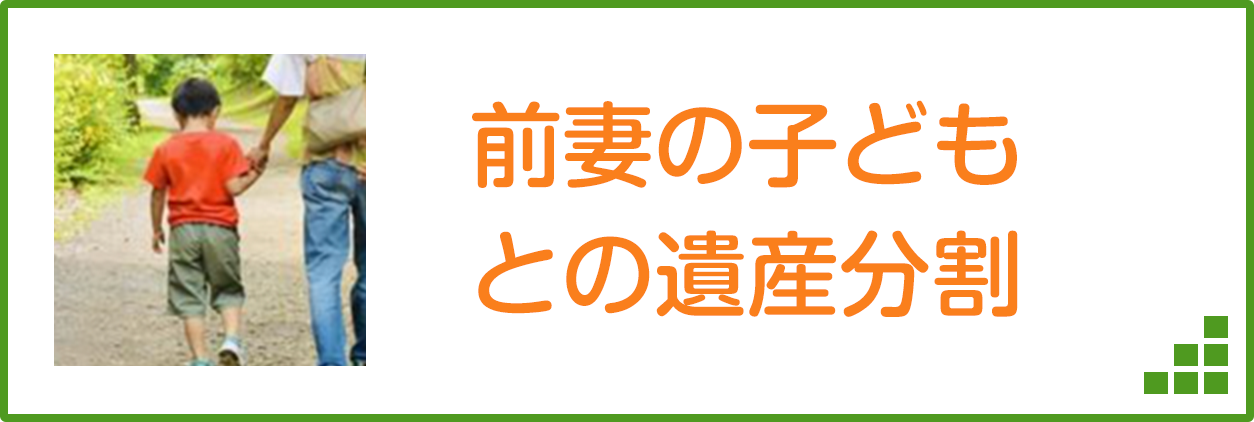
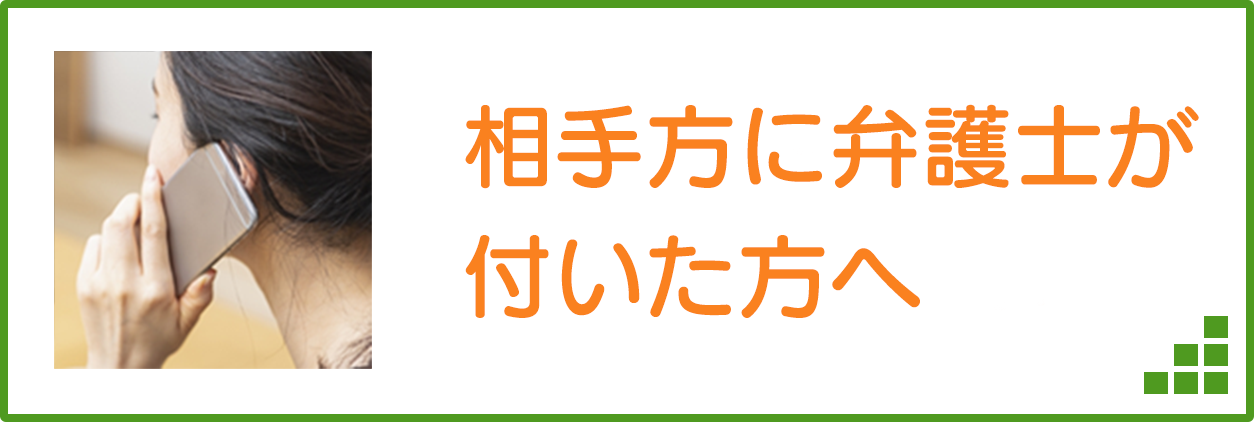
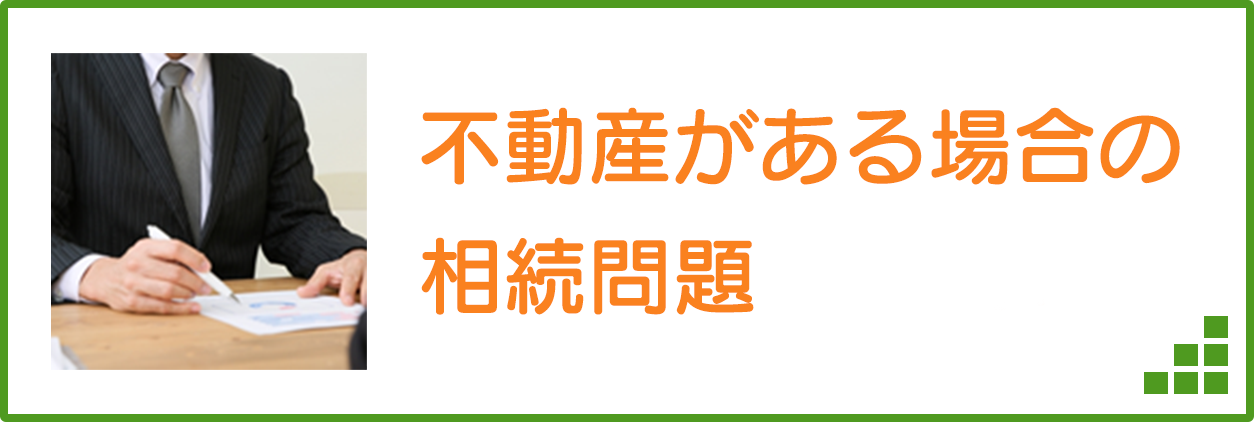


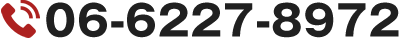






代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
リーガルサービスの提供を通じてお客様を笑顔にしたいとの思いから事務所名を「エミナス法律事務所」(笑みを為す)としました。
お客様を笑顔にするためには、出来るかぎりご希望に沿ったベストな解決を図る必要があります。
ご希望に沿ったベストな解決を図るためには、お客様のお話をじっくりと丁寧にお聞きすることが何より大切です。
そのため、当事務所では、十分なお時間を取り、まずは、お客様が抱いておられるご不安や紛争の解決方法に関するご希望を正確に理解するよう努めています。
その上で、ご不安を解消あるいは低減できるよう、ご納得いただけるまで何度でもお答えさせていただくとともに、どこまでもお客様に寄り添い、笑顔になれる解決を全力でサポートいたします。