不動産相続の名義変更に期限はある?不動産を相続したときに知っておくべき基礎知識とは?
目次
相続により、不動産を取得したときに必ず行わなければいけないこと。それが、名義変更です。名義変更をしないままの状態が続くと、後々トラブルが発生する危険性があるので注意しなければいけません。
また、トラブルが発生する危険性以外にも知っておかなければいけない情報があります。それが、法改正による義務化です。法改正により2024年4月1日から相続により取得した不動産の名義変更が義務化されました。これにより、不動産を相続した場合は必ず名義変更を行う必要がでてきたのです。
では、不動産を相続した場合、いつまでに名義変更を行なえばいいのでしょうか?
今回は、不動産を相続した場合の名義変更について詳しく解説します。本記事を読むと、相続登記の期限だけでなく、相続登記をしない場合の危険性、名義変更の流れや費用が分かるので、不動産を相続した方や、不動産を相続する可能性がある方は、ぜひご一読ください。
不動産相続の名義変更が義務化された背景
2024年4月1日から相続不動産の名義変更が義務化されました。今回の法改正の背景には「所有者不明土地」の増加が大きく関係しています。
所有者不明土地とは、名前の通り所有者が不明な土地のことです。所有者が不明とされる理由の多くは、相続登記が行われず放置されたことにあります。正しい名義変更が行われなかったことで、誰の所有物なのかを特定することができず、公共事業や民間プロジェクトに支障をきたすことになっているのです。
また、近年では空き家問題も深刻化しています。所有者が誰なのかが分からないため、土地を活用できないどころか、倒壊寸前の空き家を解体することもできません。近隣住民からは不安の声があがっているのです。
そんな、所有者不明土地は全国に410万ヘクタール以上もあるとされています。これは、九州の面積を上回るほどの広さです。
所有者不明土地が増加した背景には、相続登記が任意であったことだと指摘する専門家も少なくありません。そこで、所有者不明土地を減らし、土地を活用していくために法改正が行われ、相続登記が義務化されることになったのです。
法改正により変更された部分
先程も紹介したように、法改正により相続不動産の名義変更が義務化されました。では、この法改正により具体的に何が変わるのでしょう?ここからは、法改正で変更された具体的な内容について見ていきましょう。
名義変更を行わなければいけない期限
相続不動産の名義変更義務化で、押さえておかなければいけないポイントが期限です。今回の法改正において名義変更は3年以内と定められています。ここで注意しておきたいのがカウントの開始時期です。
3年のカウントは、相続により不動産を取得したことを知った日から開始されます。
なお、遺言書により土地の相続人になる場合や、遺産分割により複数名が相続の権利を得た場合も適用されるので、忘れずに覚えておきましょう。
10万円以下の過料
これまでは、相続不動産の名義変更を行わなくても具体的な罰則は存在しませんでした。しかし、今回の法改正では10万円以下の過料が科されることが定められています。この規定は、遺言による遺贈にも適用されるので注意してください。
ただし、3年以内に相続登記が行えない「正当な理由」があると判断された場合は、過料の対象になりません。
具体的なケースとしては、下記のような状況が該当します。
・相続人が多いことで、必要資料の収集や相続人の把握に時間がかかるケース
・遺言の有効性や遺産範囲が争われているケース
・相続登記申請義務者が事情を抱えているケース(重い病気など)
・相続登記申請義務者がDV被害者等であり、生命・心身の気概が及ぶ恐れがあるケース
・経済的な理由により、登記申請費用を負担できないケース
上記のケースに該当していなくても、個々の事情を総合的に考慮し「正当な理由」の有無が判断されると定められています。
名義変更を行わないことで抱えるリスク
正当な理由がない状態で、相続不動産の名義変更を3年以上行わなければ10万円以下の過料が科せられることは前章で紹介した通りです。しかし、名義変更を行わないことで抱えるリスクは過料だけではありません。ここからは、名義変更を行わないことで抱えることになるリスクについて詳しく見ていきましょう。
不動産の取り扱いに制限がかかる
相続不動産の名義変更が行われていなければ、登記上の名義は被相続人のままです。そのため、相続を証明することができません。つまり、他者に対して自分が所有する不動産であることを証明できないということです。
これにより、不動産の取り扱いに制限がかかります。不動産の売却や賃貸にだすことができるのは名義人だけです。そのため、名義変更が行われていない状態では売却したり賃貸にだしたりすることができません。
また、名義変更が行われていなければ上記と同じ理由により抵当権を設定することもできません。つまり、不動産を担保にしてお金を借りることもできないということです。
名義変更しておけば得られたかもしれない利益やメリットを手にすることができなくなるのは大きなリスクといえるでしょう。
相続問題の複雑化
相続不動産の名義変更を行わずに放置すると、相続関係が複雑化します。名義変更が行われないまま相続人が亡くなると、相続権は次の相続人に引き継がれていき「数次相続」状態になっていきます。数次相続状態になると、推定相続人が増えていくためトラブルが発生しやすくなるので注意しなければいけません。
数代にわたり放置した結果、推定相続人が増えていき名義変更を行うまでに2年以上の時間がかかったケースもあります。自分や家族が争いに巻き込まれない環境を作るためにも、不動産の相続人なった場合は早めに名義変更を行うようにしましょう。
相続登記の流れ
相続により不動産を取得した場合は、余計なリスクを抱えないためにも早めに名義変更を行う必要があります。では、相続登記はどのような流れで行えばいいのでしょう?ここからは、相続登記の流れを解説します。
まずは現状の名義を確認する必要があります。名義を確認した結果、被相続人の名義であることが分かれば問題ありません。しかし、名義変更が行われていなければ、誰が相続人になっているのかを把握していく必要があります。
確認した結果、被相続人の名義であることが分かれば、申請に必要な書類を集めていきます。なお、必要書類は下記の通りです。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続する不動産の登記事項証明書など
上記の書類に加え、相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議書も必要です。遺産分割協議書は、遺産の分割方法や割合などがまとめられた書類で、相続人が話し合って決めたことが記されている書類になります。法律上、作成義務はありませんが相続手続きの際には必要な書類になるので、必ず作成しておきましょう。協議の難航が予想される場合は、前もって弁護士や司法書士といった専門家に相談しておくことも大切です。
書類が揃ったら、法務局で申請手続きを行います。この時、申請書類に不備があると修正を求められるので、不安な場合は専門家への依頼を検討しましょう。なお、申請はオンラインでも可能です。
申請後、法務局が審査を行い問題がなければ2週間程度で登記が完了します。
相続人申告登記
不動産登記法の改正により相続登記は義務化されました。しかし、義務化されたといっても、さまざまなケースを想定しておく必要があります。そこで、新たに導入された制度が「相続人申告登記」です。
相続人申告登記とは、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を登記官に対して申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされることになります。
単独で申出を行うことができ、準備すべき書類も、申出をする相続人が被相続人の相続人であることが分かる範囲の戸籍謄本で足りるため、書類収集の負担が軽減されます。
相続登記を義務化したとき、想定される事態の1つが期限超過です。
相続人が多い場合や相続する不動産の数が多い場合は、遺産分割の話し合いが難航する可能性があります。また、これまで登記がされていない不動産の場合は、遺産分割協議をまとめることも大変です。そのため、期限を超過してしまう危険性があります。
そこで導入された新しい制度が「相続人申告登記」です。
「相続人申告登記」を行うと、自分が相続人であることを公示することができます。これにより、将来不動産の所有者になる可能性があることを公示できるのです。公示することで、相続登記を実施していなくても過料を科せられることがなくなります。もちろん、遺産分割協議がまとまった場合は、迅速に相続登記を実施しなければいけません。しかし、相続登記が期限内に行えない場合や、遺産分割協議が長引く場合は「相続人申告登記」を活用して対応できます。
「相続人申告登記」は相続登記が義務化された令和6年4月1日からスタートした制度なので、期限内に相続登記が難しい場合は、制度の活用を検討してください。
相続登記における押さえておきたいポイント
基本的に、相続登記は前章で紹介した流れで行われます。ただし、いくつか押さえておかなければいけないポイントがあります。ここからは、相続登記の押さえておきたいポイントを見ていきましょう。
費用の内訳
相続登記を行う場合は、必要書類の発行手数料や登録免許税といった税金の支払いが必要です。また、弁護士や司法書士といった専門家に依頼すると報酬もかかります。ここでは、相続登記にかかる費用の内訳を解説します。
相続登記にかかる代表的な費用は下記の3つです。
・必要書類の発行手数料
相続登記を申請するには、被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、住民票などさまざまな書類が必要です。そのため、必要書類の発行手数料がかかります。費用としては、1万円から2万円程度とされていますが、発行枚数や発行場所によって費用が変わるので、ある程度の余裕を持たせておきましょう。
・登録免許税
相続登記を行う際には登録免許税を支払う必要があります。登録免許税は、相続する不動産により金額が変わるので注意しなければいけません。なお、税額は下記の計算式によって算出します。
固定資産評価額×0.4%
相続した不動産の固定資産評価額が4,000万円の場合は【4000万円×0.4%】になるので登録免許税は16万円になります。
・専門家への報酬
相続手続きを弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると報酬がかかります。専門家への依頼を検討する場合は、この費用を把握しておかなければいけません。目安となる相場は10万円前後とされています。ただし、この金額は1つの目安として覚えておきましょう。なぜなら、実際の報酬額は相続関係の複雑さや、不動産の数によって変わるからです。報酬額に対して不安がある場合は、事前に見積もりを依頼して正確な報酬額を把握してから依頼しましょう。
法改正以前に相続した不動産の取り扱い
今回の法改正で対象になるのは、これから相続する不動産だけではありません。これまでに発生した相続物件にも適用されます。つまり、過去の相続も対象となるということです。相続登記の期限は不動産の相続を知った日から3年以内とされているので、中には3年を過ぎてしまっていることもあります。このような場合は、施行日である2024年4月1日から3年以内に対応すれば問題ありません。
過去の相続物件に関しては「不動産の相続を知った日から3年以内」または「施行日から3年以内」の遅い方が適用されることになっています。つまり、2024年3月31日以前に相続した不動産については2027年4月1日までに登記を完了しておけば問題ないということです。
過去の不動産物件も対象となるので、該当する場合は早期の対応を心がけてください。
専門家への依頼
相続不動産の名義変更は自分で行うこともできます。しかし、必要書類が多く遺族同士の話し合いや遺産分割協議書の作成、申請書の記入などを行う必要があるため、気軽に行えるものではありません。
また、申請書に不備があると再度作成し直す必要があるので、時間を無駄にしないためには専門家への依頼を検討するのがいいでしょう。特に、下記のような状態は相続登記が難しくなるため専門家への依頼を検討した方がいいかもしれません。
・数代にわたり相続登記を行っていない
・相続登記の期限が迫っている
・相続不動産が遠方にある
・相続不動産の数が多い
・権利関係が複雑化している
・遺族同士の話し合いがまとまらない
上記にあてはまる場合は、早めに弁護士や司法書士への相談をしておくことで、負担を軽減できる可能性があります。弁護士や司法書士に相続登記申請を依頼することで、適切なサポートが受けられるだけでなく、書類不備などで時間を無駄にすることもなくなります。
手続きに対して少しでも不安がある方は、専門家への依頼を検討しましょう。
まとめ
これまでは、相続不動産の名義変更は義務ではありませんでした。義務化されていないことで、相続不動産の名義変更が行われずに全国に多くの「所有者不明土地」が増えてしまったのです。その結果、公共事業や民間プロジェクトに支障がでるようになったのです。この状況を変えるために法改正が行われ、相続不動産の名義変更は義務化されることになりました。
名義変更を行う期限は「相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内」または「施行日から3年以内」の遅い方となります。つまり、2024年3月31日以前に取得した相続不動産については2027年の4月1日までに名義変更を行う必要があるということです。
なお、相続不動産の名義変更は自分で行うこともできます。しかし、相続人が多い場合や、相続する不動産の数が多い場合は、手続きも大変になるので弁護士や司法書士など専門家への依頼を検討した方がいいでしょう。
相続不動産の名義変更が行われていなければ、後々トラブルに発展する危険性もあります。また、過料が科せられる可能性もあるので、相続不動産を取得した場合は迅速な対応を心がけてください。
執筆者プロフィール
- 累計1300件以上の相続相談に対応し、NHKの番組でも『遺産相続問題に詳しい弁護士』としてご紹介いただきました。相続に関する書籍も多数出版しています。難易度の高い相続案件も対応可能です。初回相談では、相談者の方のお話をじっくりお伺いし、相談者の方の立場に立って考え抜き、できるだけ簡単な言葉で分かりやすく説明することを心がけています。
最新の投稿
- 2025年7月25日コラム相続人以外の貢献も報われる!「特別寄与料」と生前対策の重要性
- 2025年7月18日コラム遺産相続の相談先どこがいい?【弁護士が徹底解説】最適な専門家選びとトラブル解決の道筋
- 2025年6月13日遺書と遺言書の違いを弁護士が徹底解説!
- 2025年5月2日【相続で介護の寄与分が認められるために必要な6つの要件とは?】判例と計算方法を弁護士が解説
その他のコラム
遺書と遺言書の違いを弁護士が徹底解説!
遺書と遺言書の違いを弁護士が徹底解説! 「遺書」と「遺言書」。どちらも亡くなった方が生前に自身の想いや財産について書き残すもの、という漠然としたイメージをお持ちかもしれません。しかし、これら二つの書面は全くの別物であり、その違いを知っているかどうかが極めて重要になります。 本記事では、相続に強い弁護士が、「遺書」と「遺言書」の違いを明確にし、それぞれの法的効力、後悔しない相続を実現するた
被相続人から仕送りや生活費の援助を受けていた相続人に特別受益が認められますか?
相続・遺言Q&A相続人が被相続人から仕送りや生活費の援助を受けていたとしても、常に特別受益に該当するわけではありません。 直系血族(例:親子)及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負担しています(民877)。そのため、被相続人から相続人に対する仕送りや生活費の援助が「扶養義務」の範囲内と評価される場合、「生計の資本としての贈与」とは認められず、特別受益には該当しません。 被相続人
遺産分割調停を欠席すると何か不利なことはあるのでしょうか?
相続・遺言Q&A1 一部の調停期日を欠席する場合 お仕事や体調不良などの合理的な理由があれば、特に不利になることはありません。 ただし、必ず事前に裁判所へ連絡し、指示に従うようにしてください 2 全部の調停期日を欠席する場合 (1) 知らないうちに調停が成立してしまうという不利は生じません 遺産分割調停が成立するためには、相続人全員の参加が必要であり、欠席している相続人がいるにもかかわらず
香典は遺産にあたるか?
相続・遺言Q&A香典は、死者への弔意、遺族へのなぐさめ、葬儀費用など遺族の経済的負担の軽減などのために、喪主や遺族に対してなされる贈与であるため、遺産にはあたりません。 香典は、慣習上香典返しに充てられる部分を控除した残りの部分が葬儀費用に充てられますが、葬儀費用を支払ってもなお残余金が生じた場合は、喪主が取得すると解する説と、相続人が法定相続分に従い取得すると解する説に分かれています。
ずっと介護・看護をして面倒を見てきたなど,被相続人(亡くなった方)に貢献してきた相続人は、他の相続人よりも多く遺産を取得できるのですか?
相続・遺言Q&A他の相続人より遺産を多く取得できる場合があります。 [su_quote]被相続人の介護・看護を実際に行った相続人と、そうでない相続人との不公平を解消する制度として「寄与分」というものが法律で認められています(民法904条の2第1項)。[/su_quote] 寄与分が認められると、まずは遺産から寄与分(金銭に換算される)を差し引き、残った遺産を法定相続分に応じて分配することになるため、寄
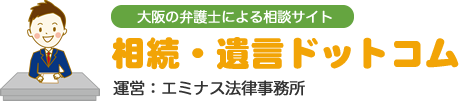
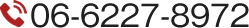



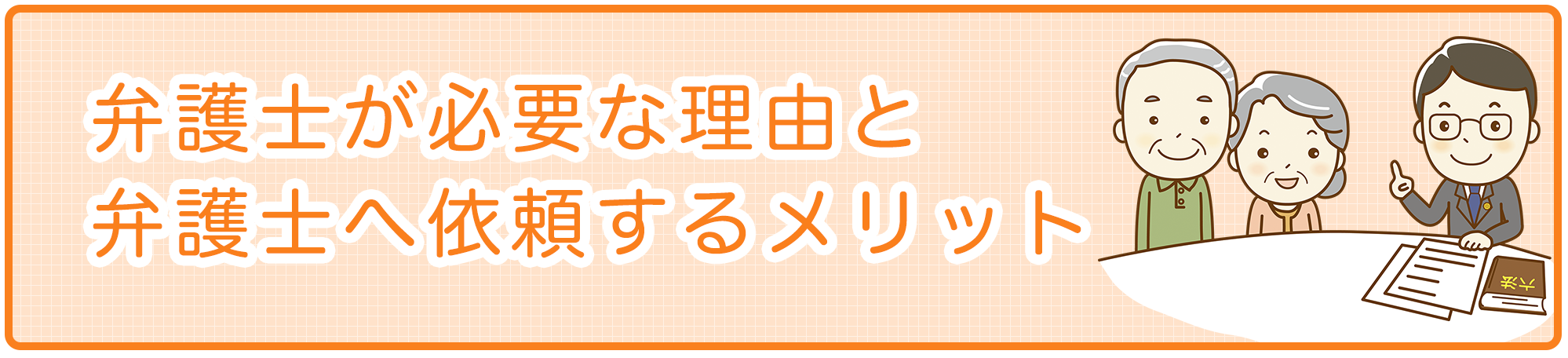
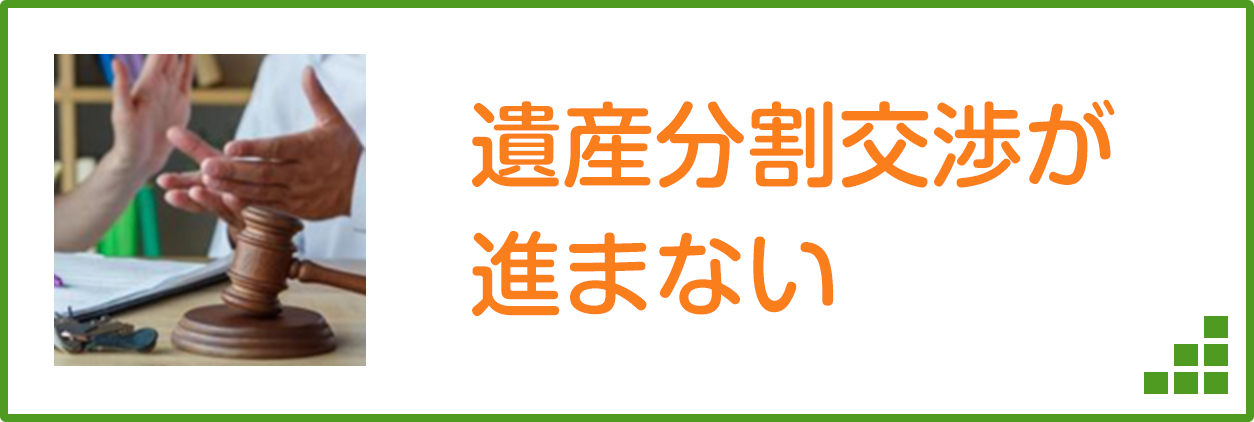

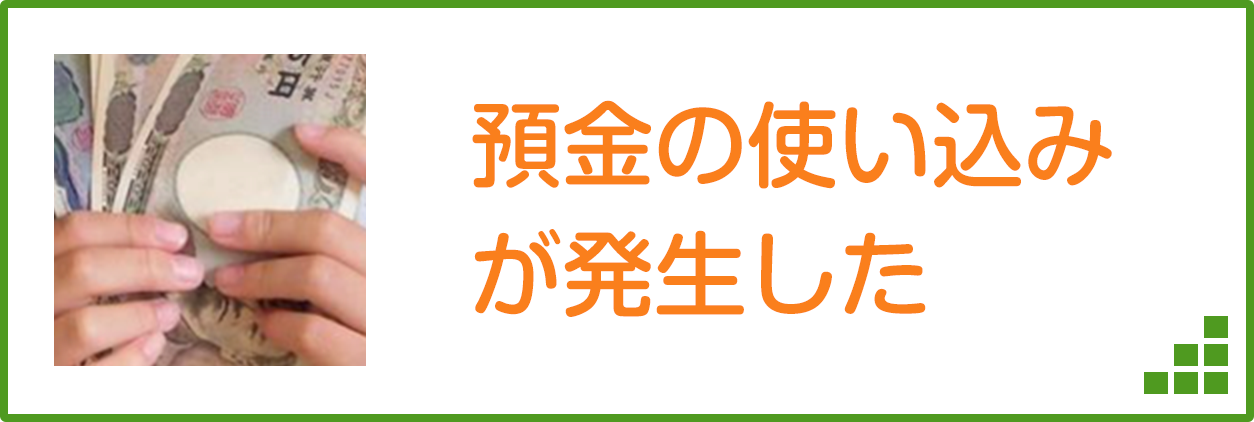

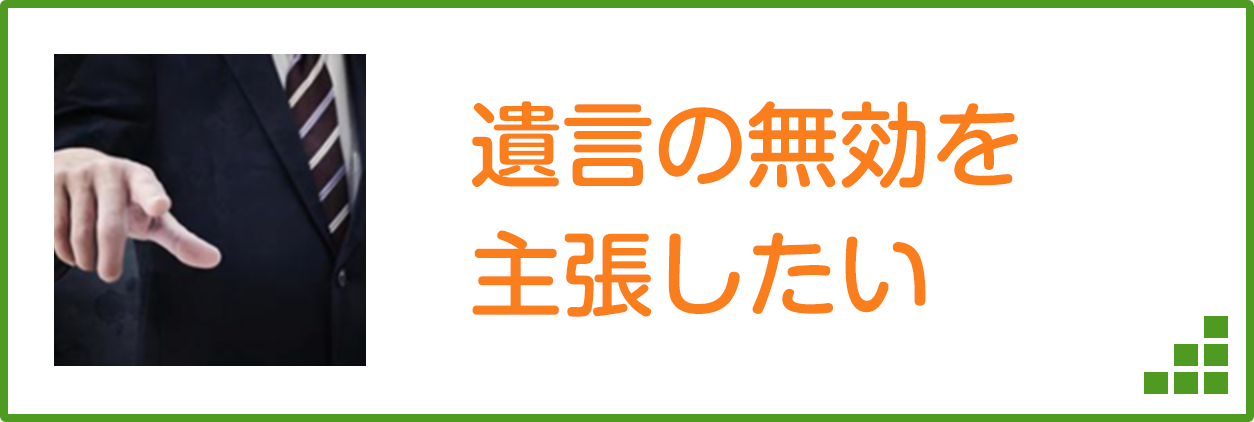
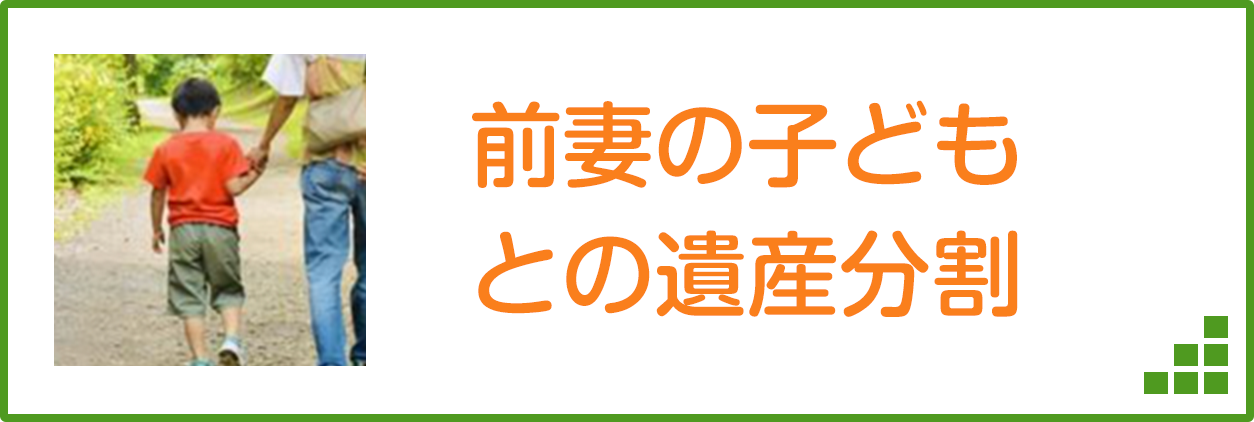
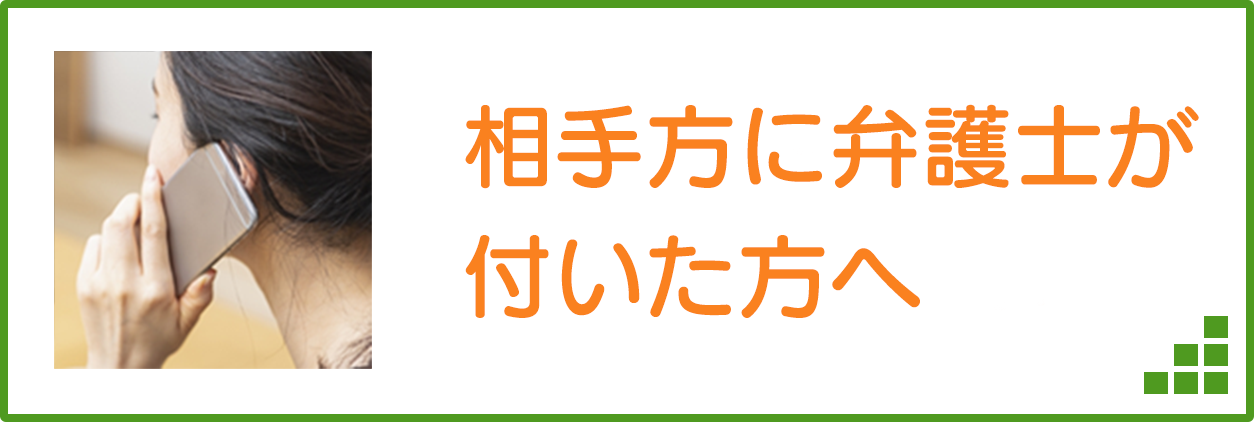
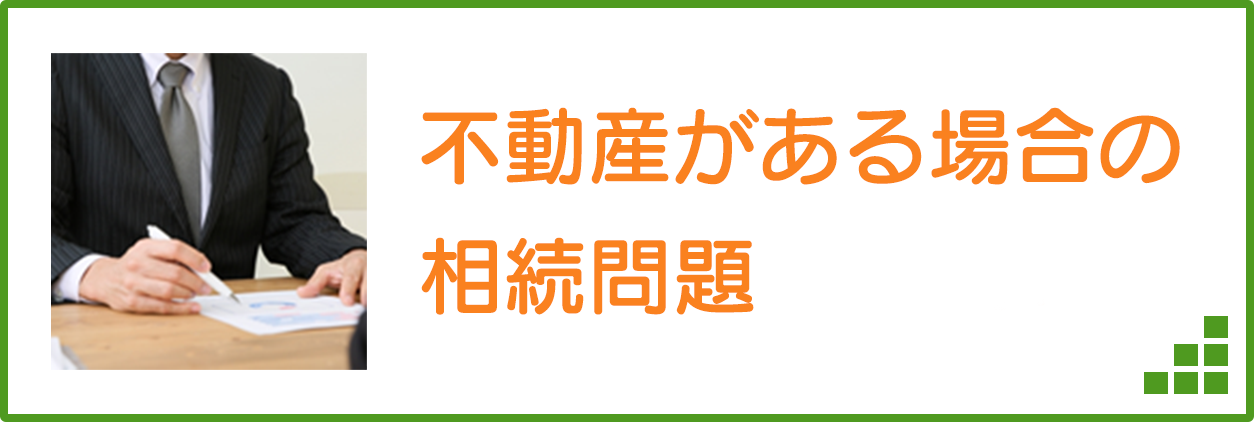


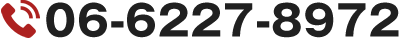






代表弁護士の新井教正(あらいのりまさ)と申します。
リーガルサービスの提供を通じてお客様を笑顔にしたいとの思いから事務所名を「エミナス法律事務所」(笑みを為す)としました。
お客様を笑顔にするためには、出来るかぎりご希望に沿ったベストな解決を図る必要があります。
ご希望に沿ったベストな解決を図るためには、お客様のお話をじっくりと丁寧にお聞きすることが何より大切です。
そのため、当事務所では、十分なお時間を取り、まずは、お客様が抱いておられるご不安や紛争の解決方法に関するご希望を正確に理解するよう努めています。
その上で、ご不安を解消あるいは低減できるよう、ご納得いただけるまで何度でもお答えさせていただくとともに、どこまでもお客様に寄り添い、笑顔になれる解決を全力でサポートいたします。