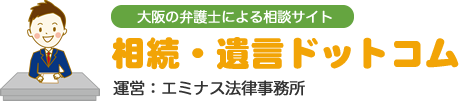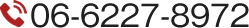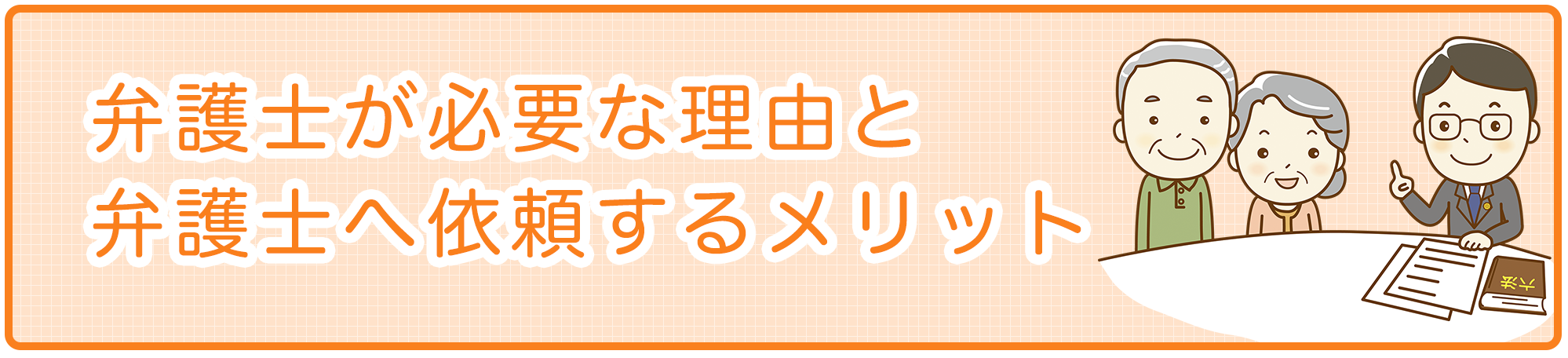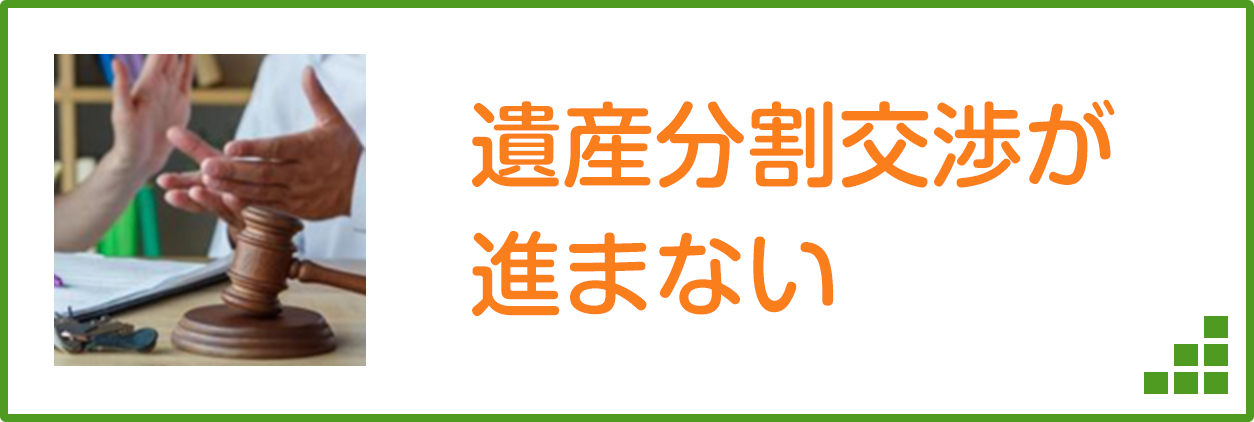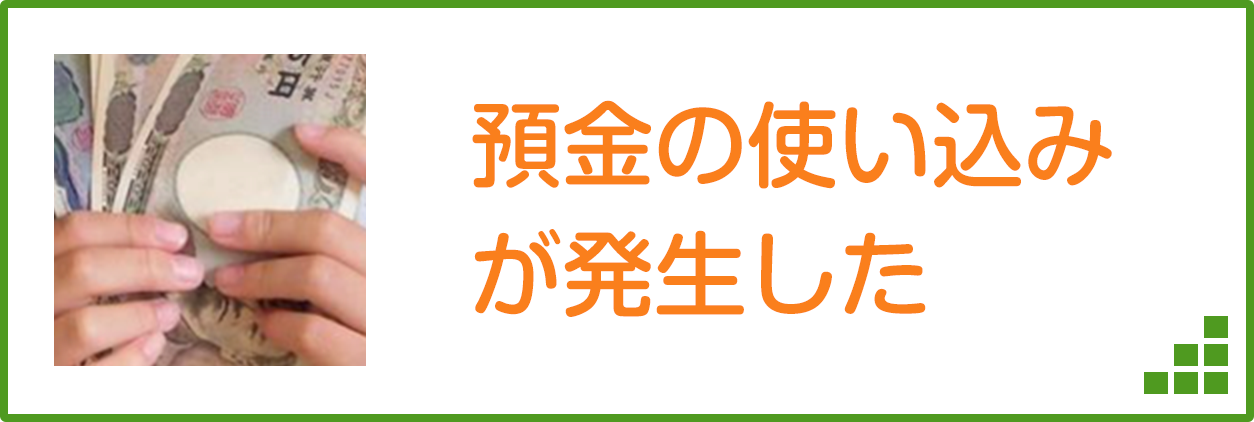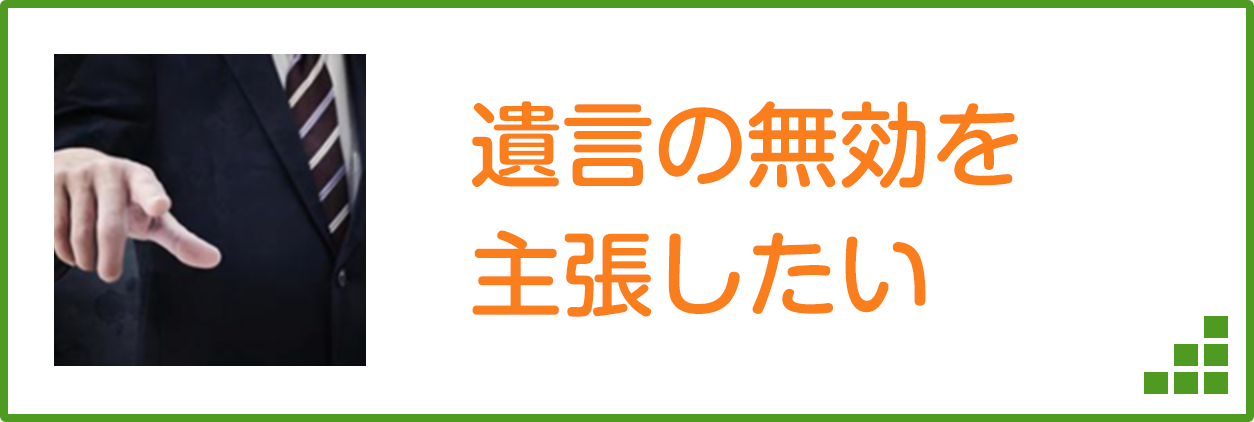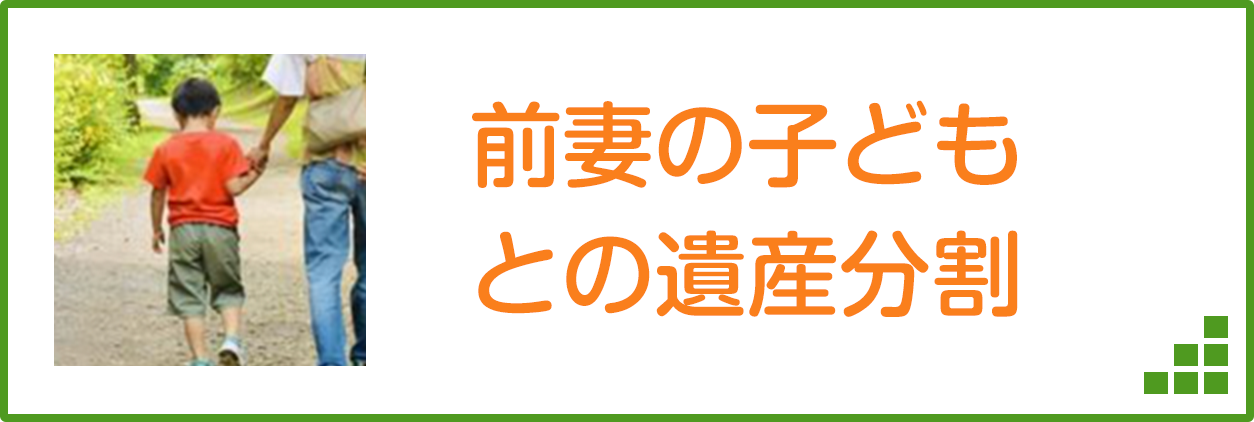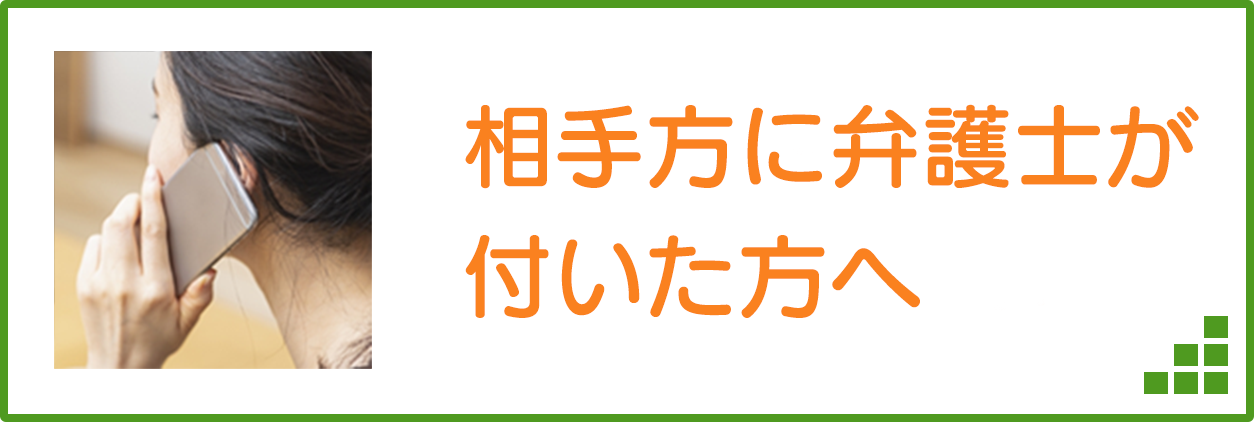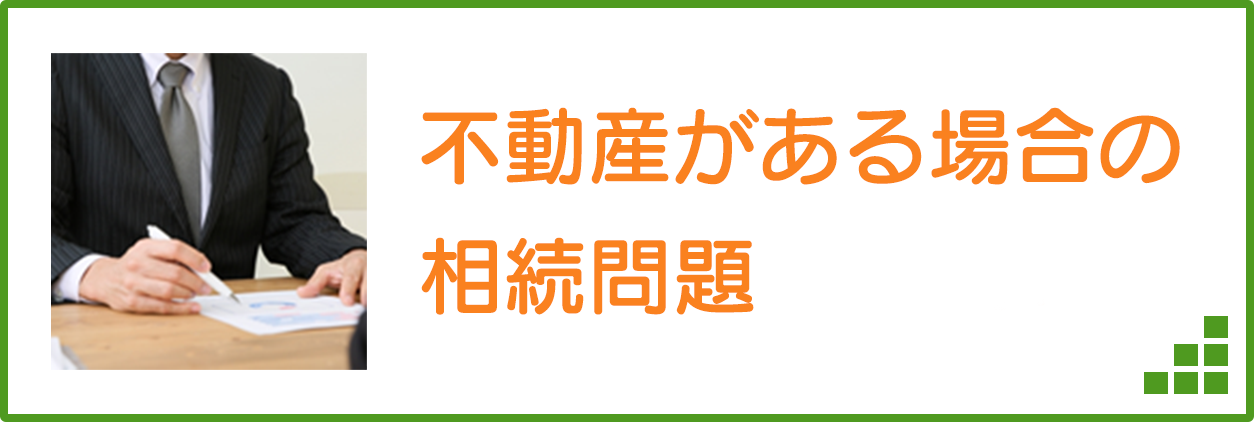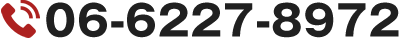ずっと介護・看護をして面倒を見てきたなど,被相続人(亡くなった方)に貢献してきた相続人は、他の相続人よりも多く遺産を取得できるのですか?
相続・遺言Q&A他の相続人より遺産を多く取得できる場合があります。
寄与分が認められると、まずは遺産から寄与分(金銭に換算される)を差し引き、残った遺産を法定相続分に応じて分配することになるため、寄与分のある相続人の取得分は、他の相続人と比べて、寄与分の分だけ多くなります。
ただ、実際には、そう簡単に介護・看護について寄与分が認められるわけではありません。
話し合いで、他の相続人があなたの寄与分を認めてくれれば問題ありませんが、他の相続人からすれば、あなたの寄与分を認める=自分の取得分が減る、という結果となるため、他の相続人があなたの寄与分を認めようとせず、相続トラブルになってしまうことも少なくありません。
寄与分については、要件に該当するのか,寄与分をどのように金銭に換算するのか、どのようにして寄与分を立証するかなど,相手方や裁判所に認めさせるためには専門知識と経験が必要になってきます。
そのため、寄与分の主張を行いたいとお考えの場合は、弁護士に相談することを強くお勧めいたします。
当事務所では,累計1000件以上の相続相談に対応し、寄与分を巡る相続紛争についても豊富な知識と経験があります。お悩みの方は,是非一度,当事務所にご相談ください。
執筆者プロフィール
- 累計1300件以上の相続相談に対応し、NHKの番組でも『遺産相続問題に詳しい弁護士』としてご紹介いただきました。相続に関する書籍も多数出版しています。難易度の高い相続案件も対応可能です。初回相談では、相談者の方のお話をじっくりお伺いし、相談者の方の立場に立って考え抜き、できるだけ簡単な言葉で分かりやすく説明することを心がけています。
最新の投稿
- 2025年7月25日コラム相続人以外の貢献も報われる!「特別寄与料」と生前対策の重要性
- 2025年7月18日コラム遺産相続の相談先どこがいい?【弁護士が徹底解説】最適な専門家選びとトラブル解決の道筋
- 2025年6月13日遺書と遺言書の違いを弁護士が徹底解説!
- 2025年5月2日【相続で介護の寄与分が認められるために必要な6つの要件とは?】判例と計算方法を弁護士が解説
その他のコラム
被相続人から仕送りや生活費の援助を受けていた相続人に特別受益が認められますか?
相続・遺言Q&A相続人が被相続人から仕送りや生活費の援助を受けていたとしても、常に特別受益に該当するわけではありません。 直系血族(例:親子)及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負担しています(民877)。そのため、被相続人から相続人に対する仕送りや生活費の援助が「扶養義務」の範囲内と評価される場合、「生計の資本としての贈与」とは認められず、特別受益には該当しません。 被相続人
「死んだらあげるから」という口約束は有効?
相続・遺言Q&A遺言は一定の方式に従って書面で作成する必要があるため、遺言としての効力は認められません。 しかしながら、死因贈与(=贈与者の死亡によって効力を生じる贈与)として効力が認められる可能性があります。死因贈与は契約であり、契約は口頭(=口約束)でも成立するためです。 問題は、口約束があったことを立証できるかです。 口約束をした時のやり取りが録音・録画されている場合、立証は容易であり、また、
預貯金を使い込まれてしまった場合の対応方法を教えて下さい。
相続・遺言Q&A最も重要なのは、預貯金が使い込まれていることを示す証拠の収集と分析です。 相続人の一部の者による預貯金の使い込み(使途不明金)があった場合、他の相続人は、預貯金を使い込んだ相続人に対して、その返還あるいは損害賠償を請求することができます。 交渉で相手方に預貯金の使い込みを認めさせ、あるいは、裁判において生前の預貯金の使い込みがあったと認定してもらうためには、証
遺産分割調停を欠席すると何か不利なことはあるのでしょうか?
相続・遺言Q&A1 一部の調停期日を欠席する場合 お仕事や体調不良などの合理的な理由があれば、特に不利になることはありません。 ただし、必ず事前に裁判所へ連絡し、指示に従うようにしてください 2 全部の調停期日を欠席する場合 (1) 知らないうちに調停が成立してしまうという不利は生じません 遺産分割調停が成立するためには、相続人全員の参加が必要であり、欠席している相続人がいるにもかかわらず
認知症の父が作成した公正証書遺言を無効にできますか?
相続・遺言Q&A無効にできる場合があります。 遺言が無効となる理由はいくつかありますが、代表的な理由は以下の3つです。 ① 遺言書が民法所定の方式に違反している場合 ② 遺言者に遺言能力がなかった場合 ③ 遺言書が偽造された場合 認知症の方が作成された遺言書の無効理由としては、まずは②の遺言能力の有無を検討することになりますが、遺言能力の有無の判断